A5判 296ページ 並製 ISBN978-4-88325-421-7 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年09月 書店発売日:書店発売日:2010年09月15日
1800円+税

ずっと前々から夢だったこと。それは直接トーハンや日販に新刊がドーンと発送できることでした。
一般読者にはわからないことでしょうが、実はこれまでは、地方小出版流通センターさんに送った本が、書店の注文に応じてトーハンや日販に送られ、それから書店に回るため、県外書店さんへ届くのはおそらく最短で1週間かかっていたと思います。
今回はデータ登録を先にしてもらうため、地方小さんに見本出しをお願いしました。明日、本は取次さんに届き、自動仕分機で注文データに沿って書店へ送られるとか……。
ちなみに愛知県の人口は700万人だから、実に滋賀県の5倍なんですね。
いつも、いつも発売日がどんどん遅れていたけど、今回は編者のTさんの熱意で順調に仕事が進みました。本当にありがとうございます。
『愛知の山城ベスト50を歩く』発刊を記念して、今回の本の編者である愛知中世城郭研究会主催の講演会が開催されます。是非お出かけください。
シンポジウム
「戦国から織豊、そして近世城郭への道」
と き 2010年10月2日(土)
9:30~16:40(受付9:00)
ところ 岡崎市福祉会館6階ホール
岡崎市十王町2丁目9番地岡崎市役所内
参加費 1000円 資料代 500円
主 催 愛知中世城郭研究会
詳しくはシンポジウムチラシをご覧ください。

この閻魔さんは「血噴き地蔵」と呼ばれています。江戸時代に土砂流でうつ伏せに倒されていた石を石屋さんが、これはよい石だと思って割ったところ、帰ってから肩が痛くなって、石から血が流れている夢を見ました。翌朝早く、石を見に行ってひっくり返してみたところ石像が彫ってあったといういわれによるものです。
地蔵菩薩は子供を救うとか災難を救うという意味で彫られます。また、地獄に送るとか極楽へ導くためにいろいろ諭され、修行を助けられるのが閻魔さんですが、地蔵さんの化身が閻魔さんです。
閻魔さんは、ほとんどが絵に描いてあるか木彫りです。石彫りは国内にほとんどなく珍しいものです。右側3分の1は別石で修復されています。いわれのように石を割ってしまったので、残る部分に合うように彫ったものですが、修復に用いた石の質も厚さも元の物とは異なり、近くで見ると時代の違いがはっきりとわかります。これらは離れないようにくさびが打ってあり、裏には穴が開いていて、鉄の股釘を差し込めるようにしてあります。
写真の右側の像は、合掌している僧形、左側が阿弥陀仏です。下の段には、右側に錫杖と宝珠を持った地蔵、左側は袈裟を斜めにかけ数珠を持った僧形です。全体の形として将棋の駒形というのは珍しいものです。
下段中央には
浄西院秀阿弥陀仏行大徳宗舜 敬白
と彫られています。裏に「延長二年甲申」(西暦では924年)とあったそうですが、今は読めません。
在所の一番下の村を寺村町といいますが、ここの人たち、特にお婆さんたちが掃除や花を供えたりしています。毎年、菩提寺の四つの寺が協力して、年番で小学生たちに白い象の姿をした甘茶の山車を引かせて花祭りの行事を行い、供養しています。
閻魔像の辺り一円は、花崗岩の土砂が流れ込んでいて今はなだらかな傾斜になっていますが、元は平坦地だったところです。これは、古絵図に示されているように少菩提寺の施設があったということで、閻魔像より上の方にも多くの平坦地が残っています。
儀平塾主宰 鈴木儀平
●この文章は、生前の鈴木さんの講義を録音したテープから起こしたものです。
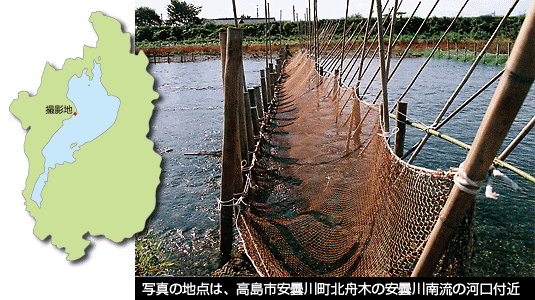
10月も下旬頃になると、朝夕はめっきり気温が下がって、時折、湖上を北西の強風が吹き抜けるようになる。12月の始めにかけて、こんな荒れた日やその翌日には、体を紅色に染めたアメノウオが、琵琶湖から産卵のために川を上ってくる。アメノウオとは、万葉の昔からのビワマスの呼称で、この魚を捕獲するために川に仕掛けられるのが「ますヤナ」である。また、ビワマスとは、成長すると全長60㎝にもなる琵琶湖だけに生息するサケ科の魚である。
琵琶湖のヤナというと安曇川河口に設置されるアユのカットリヤナがよく知られているが、おそらく古代から近世に至るまで、川の河口や内湖の出口にはどこでも、サイズや構造が異なるさまざまなヤナが仕掛けられ、湖と川や内湖の間を移動する魚類が漁獲されていたものと思われる。ヤナという漁具は、魚が獲れるかどうかは魚まかせのところがあるが、ヤナを設置する権利を得ると、待っているだけで魚が手に入るという便利なものである。そのために、ヤナの漁業権を得ることは、その地域のかなりの実力者でその時代の権力者と結びつきをもった者でないとかなわなかったものと考えられる。写真は、安曇川の南流に北船木漁業協同組合によって今も設置されている「ますヤナ」である。北船木漁業協同組合では、毎年10月1日に、京都の上賀茂神社へビワマスが現在でも献上されており、古代の結びつきの名残がうかがわれる。
ところで、安曇川の「ますヤナ」が「今も設置されている」と断ったのは、かつて琵琶湖では各所で見られたこのヤナが、どんどん消えているからである。小さな川のヤナはほとんど消えたし、大きい川でも私が知っているだけでもこの20年ほどの間に犬上川、愛知川、知内川、百瀬川などのアユやマスのヤナが消えている。
時代の流れとは言え、ヤナに限らず恐らく数千年の歴史をもち、その権利を得るためにどれほどの犠牲や労力が払われたか知れないヤナなどの漁業権やそれを行使する漁労文化・技術がなくなってきていることは寂しい限りである。アメノウオを獲るための「ますヤナ」も、もう写真の安曇川の南流のものしか残っていない。魚の減少にともなって、生業としてのヤナ漁が成り立たなくなってきているのである。琵琶湖の在来種を増やし、漁業としてのヤナ漁が存続するようにすることが必要である。
滋賀県水産試験場 場長 藤岡康弘
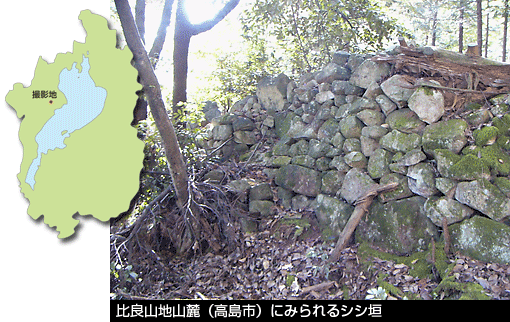
シシ垣は、漢字で「猪垣」、「鹿垣」、「猪鹿垣」と書く。シシとは、肉がとれる獣類の古い呼称である。古くから、イノシシやシカは山間の住民にとって貴重なタンパク源であったが、一方で農作物に多大の被害を与える害獣でもあった。シシ垣は、これらの獣が田畑に侵入してこないように築かれた垣のことである。江戸時代などに築かれた石積みや土盛りのシシ垣の遺構が、今でも各地に残っている。
滋賀県内にも、もちろんみられる。しかしこれまで、豪族や武士にまつわる古墳や城郭といった遺構が脚光を浴びてきたのにくらべ、農民の汗の結晶ともいうべきシシ垣が注目されることはなかった。
たとえば比良山地の山麓には、地元でとれる花崗岩の石を積んだり、土を盛ったシシ垣がみられ、北部の高島市周辺には、長さが8にもおよぶものがある。また、「ヤマトタケルと白イノシシ」の神話が残る伊吹山にも、石灰岩を積んでイノシシやシカの畑への侵入を防ごうとしたシシ垣が残っている。さらに特徴的なものとして、大津市(旧志賀町)の荒川地区には、イノシシやシカの侵入に加え河川の水害・土石流災害に備えたシシ垣が残っている。
シシ垣と道が交わるところには木戸口といわれるものがみられ、朝夕において、通行人は戸締りを厳重に行う必要があった。戸締りとは、木戸口からイノシシやシカが入ってこないように頑丈な板などをはめることであった。
シシ垣はこれまで注目度が低かったが、注目される必要がある。地域の財産であり、子供や大人の学習の教材にもなる。先祖がどのようにして獣と向き合ってきたのか、その苦労に思いをはせ、今日の獣害への対応の教訓にすることができる。シシ垣に関心があるかたは、私がつくっている左記のシシ垣ネットワークのホームページにもアクセスしていただければ幸いである。
(http://homepage3.nifty.com/takahasi_zemi/sisigaki/sisimein.htm)
奈良大学文学部地理学科 教授 高橋春成

山歩きには、景色や花を愛でる、山菜を味わうなど、楽しみがいろいろとある。いささかマニアックではあるが、哺乳類に興味を持つ者にとっては、ニホンジカの落角拾いも楽しみの一つである。
ご存知のようにニホンジカの角は雄にしかなく、毎年春には根元からはずれて落ち生えかわる。かつて湖東の霊仙山に通っていた頃、この時期にここに行けば角が拾えるという秘密の場所が何カ所かあった。角の長さから持ち主の体重を推定できるなど、標本として活用するのが目的ではあるが、収穫の楽しみもあった気がする。
ふつう鹿角はどれでも同じ形と思われがちだが、意外やこれが不揃いなのである。太さ長さはもちろんのこと、曲がり具合、分岐している枝角の数や間隔など同じものがない。袋角の時期の傷が原因とも言われるが、頭骨ごと拾った角(落頭というべきか?)でも左右で形がわずかに違っている。闘いの最中にぽっきりと折れたようなものもある。持ち主たちは、他個体に対して見栄えがすれば、不揃いでも問題ないのかもしれない。哺乳類の体は左右対称であるとはいうものの、実際には揃っていることの方が不自然なことなのかもしれない。
ニホンジカの角は年ごとに落角するものの、加齢とともに大きくなり、枝角の数も増えていく。1、2歳の雄はゴボウに似た一本角をもち、「ゴンボサン」と呼ばれることがある。成獣になると枝角は2本、3本と増えていき4本の枝角となる。さらに歳を重ねると、枝角が四本以上となったり、変形したりすることもある。単純に何歳なら枝角は何本と言えないが、角は時間とともに変化し、ますます不揃いさを増していく。
一方で落角は哺乳類にとっての大事な栄養源となる。まれに先端が削られた落角を拾うことがある。どうも他の哺乳類がかじった跡のようだ。誰が何のために……なんと犯人はニホンジカご本人のこともあるようだ。半年後に再び立派な角を持つためには、カルシウムの固まりである落角を見逃す手はない。落ちている角を少しずつかじって自分の角を再生する、みごとなリサイクル術といえる。
落角を見つけるとうれしくてすぐ拾ってしまうが、その前に写真を撮り観察することをすすめしたい。ニホンジカの生活を想像させてくれる静かなひとときを過ごすことができる。これも山歩きの楽しみの一つといえるかもしれない。

今から約30年前、その当時、滋賀県にイヌワシが生息しているとは誰も知らなかった。野鳥を観察する者にとって、イヌワシは「高山の幻の鳥」以外の何者でもなかった。
長野県のアルプス以外の東中国山地の氷ノ山(鳥取県と兵庫県の県境にあり、標高1510m)にもイヌワシが生息していることを知った私は、その近くの鳥取大学に入学することを決めた。1973年5月5日、生まれて初めてイヌワシの姿を見た。真っ青な青空を切り裂くように流れる漆黒の流体。それがイヌワシだった。あくまでも力強く無駄のない飛翔、生態が未知であることに衝動を覚え、イヌワシを観察するために中国山地に通う日々が続いた。
もしかして、滋賀県にもイヌワシは生息しているかもしれない。3年近く中国山地でイヌワシを観察して、そう思った。なぜなら、同じような環境は滋賀県の山岳地帯にもあるからだ。5万分の1の地図を穴が開くほど見つめ、イヌワシがいる確率の最も高い場所を絞り込んだ。1976年3月24日、快晴。鈴鹿山脈の奥深い山中を腰まである積雪をラッセルし、見晴らしの聞く尾根にたどり着いた。そして13:00、ついに三角形をした黒い流体が尾根上を流れるのを発見。これが、滋賀県で初めてのイヌワシの生息確認の瞬間だった。
しかし、滋賀県でイヌワシが繁殖していることを確認するのには時間がかかった。その年に抱卵中の巣が見つかったものの、雛は孵化しなかった。翌年もこのペアは繁殖には成功しなかった。何とか雛を育てていることを証明したい。地図をたよりに新たなペアを探した。そして、ついに1978年5月7日、雛のいる巣を発見。
調査を進めていくうちに、イヌワシの生息地に住む人の中には、イヌワシという名前は知らなくてもイヌワシの存在を知っている人がいることがわかった。またイヌワシがよく止まる岩には天狗岩という名前がついているし、天狗伝説が各地にあることもわかった。イヌワシは漢字で書くと「狗鷲」。琵琶湖の源流である滋賀県の森林には、古くからイヌワシが棲み、人々は山岳地帯の守護神や超能力を持つ生き物として、イヌワシを見つめ続けてきたのだ。
アジア猛禽類ネットワーク 山崎 亨


ヤママユはヤママユガあるいは天蚕とも呼ばれ、ヤママユガ科に属する大型の蛾の仲間で、日本、台湾、韓国、中国、ロシア、スリランカ、インドおよびヨーロッパに分布し、滋賀県の里山にも多く棲息しています。幼虫は、里山に生えているクヌギ、アベマキ、コナラなどのいわゆるドングリの木の葉を食べて育ちます。1年に1回だけ発生する蛾で、卵の状態で越冬します。近畿地方では、餌となるクヌギなどが萌芽する4月中・下旬頃に孵化し、4回の脱皮を経て終齢幼虫となり、6月上・中旬頃、孵化から50~60日で葉を数枚綴り合わせて営繭(繭づくり)を開始し、葉と同色の繭をつくります。
この繭は高価な緑に輝く天蚕糸の原料になります。長野県穂高地方では江戸時代の天明年間(1781~89)から天蚕の飼育が始められました。美しい光沢をもつ天蚕糸は、今も「繊維のダイヤモンド」と呼ばれて珍重されており、長浜市力丸町(旧浅井町)では1982年に浅井町天蚕組合を発足させ、天蚕繭の生産から天蚕糸を用いた加工品づくりまでの一環した事業に取り組んできましたが、現在は活動を休止しています。しかし、新たに東近江市上二俣町(旧永源寺町)でもクヌギを植栽して天蚕の大量飼育の準備を始めています。
天蚕の交配組合せの中から、左半分がメス、右半分がオスの奇妙な蛾が出現してきました。天蚕の生きたままの雌雄型は、世界で初めての写真です。天蚕の雌雄型の報告は、今までで2~3例しかありませんが、すべてが死んだ標本の写真です。
昆虫には、細胞分裂の際の生殖細胞の異常によって体の雌雄の特徴が混じり合ったものが生まれることがあります。オスとメスの混ざり方は、左右半分、上下半分など様々で、これは細胞分裂のいつの時期に起こるかによって決まります。これを雌雄型または雌雄モザイクといい、専門用語でジナンドラモルフォといいます。生殖器が雌雄型になると、蛾の体の中で、精子と卵の両方をつくります。
天蚕のメス蛾は、前翅の先が丸く、触角が細くなっています。一方、オス蛾は、前翅の先がとがり、触角が太く、櫛状になっています。雌雄型では、左では前翅の先が丸くなり、触角が細くなり、右では前翅の先がとがり、触角が太い櫛状になっています。今回2頭の雌雄型が出現しましたが、1頭はメス腹で卵巣が発達していましたが、もう1頭はオス腹で卵巣が発達していませんでした。
昆虫の雌雄型の報告は、クワガタムシやカブトムシなどの甲虫類やアゲハチョウなどの蝶類などで若干あり、その出現率は一般に1万分の1程度であると言われています。
東近江地域振興局農産普及課 寺本憲之