2010年 7月 30日
小町伝承が残る中世の宿場「小野宿」
鎌倉時代に阿仏尼(藤原定家の子)が書いた『十六夜日記』や『太平記』『実暁記』では宿場としての小野の地名を見ることができます。中山道の原型は古代最大の幹線道路「東山道」であったと推測されており、小野は早い時代から宿場の機能を果たしていました。原から小野の集落に入る街道の傍にたたずむ小さな祠の中には小町地蔵とよばれる1体の地蔵さまが安置されています、この祠は小町塚と称され小野小町伝承を伝えています。京都から北陸・関東へ往復していた当時の公人たちが小野宿にたびたび宿泊していたことから生まれた伝承であろうと考えられます。小野小町に関する伝承地は全国に25ヶ所以上存在し、絶世の美女であったといわれるだけにその伝承も多いのです。
小野町に伝わる話では、小野好実が奥州最上・出羽の郡司の任期を終えて京に帰る途中、小野に滞在し、ここの住人から1人の娘をもらい受け、京につれて帰り、養育して養女にしたのが、後の小町であったというものです。出羽守小野好実は、滋賀郡志賀町に祀られる小野 篁 の二男ですが、好実の娘が小町であるという真偽のほどは不確かであると考えられています。
小野小町地蔵付近には、明治の中頃まで茶屋があったと伝わりますが、現在は、名神高速道路と新幹線そして旧中山道がもっとも接近する所です。文明の喧噪の中にひっそりたたずむ美女伝承は、旧道ならではの趣といえましょう。
小野宿がいつ頃から宿場の機能を果たしていたのかは不明ですが、大堀あるいは原周辺の鳥籠駅と山東町の横川駅の間に位置した中世以来の駅(宿場)であったことは確かです。このような小野宿も、関ヶ原の戦い後には、攻撃を受けた佐和山城の影響で、集落ごと焼き払われてしまいました。小野で本陣を務めていた寺村家はその後旧鳥に移り、引き続き本陣を務めました。


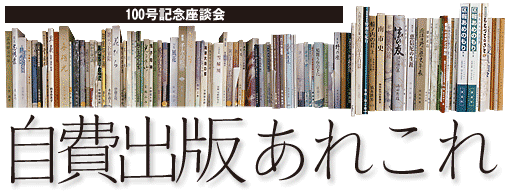



 サンライズ出版
サンライズ出版