2010年 8月 30日
奈良時代の製鉄遺跡と鳥居本
かつて、鳥居本の地名で呼ばれていた地域は、現在の旧鳥のことで、江戸時代に中山道の宿場町が誕生すると、佐和山山麓の村々が街道沿いに移転し、現在のように街道を中心とした鳥居本宿場町が形成されてきました。国宝彦根城を有する旧彦根町は井伊家が彦根藩主となった近世に誕生したまちですが、彦根市の中でも旧犬上・愛知郡に属していた集落や、坂田郡に属していた鳥居本村などは、旧市内地より早くから人々が住まいしていたとされます。
彦根市の歴史を語る史料でもっとも古いものが、鳥居本から琵琶湖に注ぐ矢倉川下流域から出土した縄文土器で、彦根周辺には縄文時代からの歴史が残ります。霊仙山麓の扇状地である鳥居本には、古来より人々の生活があったと考えられる遺跡の存在が確認されていますが、残念なことに十分な調査が行われていません。唯一、1996年に最終処分場建設に際して行われた調査から、中山町キドラ遺跡が奈良時代の製鉄遺跡であったことが判明し、近くには鍛冶に関係すると考えられる遺構が検出されました。
飛鳥時代、奈良時代頃には男鬼・武奈・仏生寺・荘厳寺など霊仙山麓の集落に寺院があり、東山道の街道に面していた原や小野には古い時代からの多くの伝承が伝わるなど、鳥居本の地は600年頃からの歴史や文化が残る地域です。当時、鳥居本の大部分は「小野庄」に、武奈・明幸は「箕浦庄」に属していました。
中山道の宿場町

江戸時代は鳥居本がもっとも栄えた時代で、中山道の宿場として街道沿いには商家や旅籠が連なった。宝暦年間に建ったといわれる有川家は当時の繁栄を物語る
豊かな田園が広がる鳥居本の平野部もかつては、琵琶湖の内湖で、山田神社付近まで内湖が迫っていたようです。鳥居本村であった頃の地形は、今と大きく異なり、鳥居本は山々と内湖に挟まれた狭い土地でした。こうした地形的な要因によって、東西文化が行き交う重要な交通の要衝として発展してきました。そして、また壬申の乱をはじめ、幾たびも戦火にまみえることにもなりました。中世になって佐和山城が築かれると、よりその傾向は顕著となりましたが、佐和山城が落城し、彦根の城下町が整備されると彦根藩の支配下で明治維新まで大いに繁栄しました。宿場町鳥居本には、街道を行き交う人々相手の旅籠や商家が生まれ、赤玉神教丸や合羽など鳥居本の名産も誕生しています。
鳥居本村の成立
明治維新後の廃藩置県によって鳥居本を支配していた彦根藩は消滅し、新たに彦根縣が設置され彦根知事に井伊直憲が任命されます。そして明治7年(1874)に百々、西法寺、上矢倉の3ヶ村が旧鳥居本と合併して鳥居本村が誕生し、明治22年(1889)には下矢倉、甲田、古西法寺、宮田、中山、荘厳寺、仏生寺、武奈、男鬼、小野、原の各村が合併して坂田郡鳥居本村になり、昭和27年に彦根市に合併するまで60年間続きました。
明治以降、新しい交通機関の発達は鳥居本に大きな影響を及ぼし、交通の重要地点が米原に移ると、鳥居本のかつての繁栄は見る影もなく寂れましたが、地域内の結束は堅く、活発な青年団活動や協同経営による産業振興策が展開されました。
郡域を超えて彦根市の合併
昭和6年、近江鉄道鳥居本駅の誕生は村民の大きな喜びでした。そして新しい交通手段の登場は、当時の鳥居本の産業振興に大きな成果がありました。しかし、鉄道から道路輸送中心の時代が到来すると、鳥居本村は大きな岐路を迎えることとなります。国道建設をも視野において彦根市との合併問題が発生し、単独中学校の建設の問題を抱えて、合併の是非を問う住民投票の結果、昭和27年(1952)に彦根市に合併しました。彦根市の面積の25%を占める鳥居本は、豊かな自然に恵まれた地域ですが、合併後50年を迎えた今、新たな将来展望の計画の必要性に迫られています。
鳥居本小学校
明治19年11月1日小学校令が実施され、今まで各集落ごとにあった学校が廃止され鳥居本尋常科小学校、鳥居本簡易小学校として開校しました。明治24 年4月1日小学校令が改正され、原、荘厳寺、武奈、男鬼の学校が廃止され、鳥居本全村を通学区域とする鳥居本尋常小学校となりました。明治31年4月には高等科を設置し鳥居本尋常高等小学校と改称。昭和16年4月1日国民学校令により鳥居本国民学校と改称。昭和22年の新教育制度6・3・3制の学制実施により昭和23年4月1日から鳥居本小学校と改称され現在に至っています。






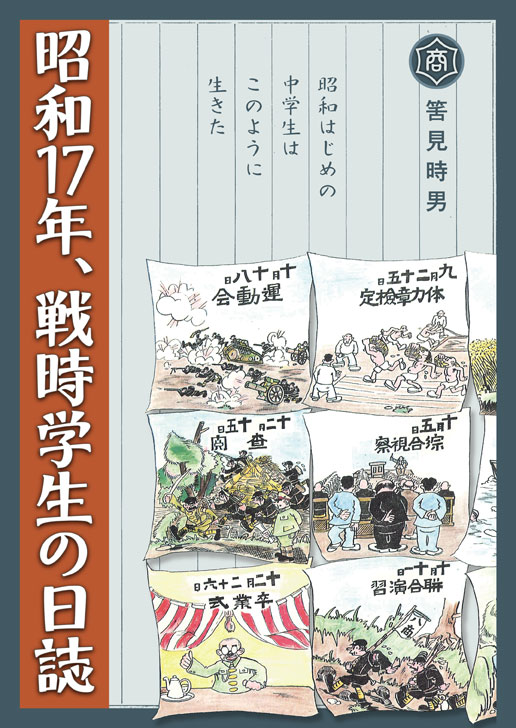
 サンライズ出版
サンライズ出版