2012年 12月 6日
オノミユキの「マンガ展覧会」
『山村大好き家族 ドタバタ子育て編』の発刊と連動して、著者・オノミユキさんのマンガの原画展が開催されます。場所はというと……、なんと、朽木の銀座街・市場から車で20分の木地山です。
と き 2012年12月7日(金)~9日(日)
ところ 高島市朽木木地山
「風と土の交藝 in 琵琶湖高島2012」の41番会場として出展です。
入場には「風のパスポート」を高島市のパスポート販売所で購入してください。
詳細地図や他の約40箇所の会場一覧が掲載されています。
マンガでいろいろ描かれている朽木や木地山ってどんなところなのかを体感しながら、ドライブ。そして、あのマンガの数々が展示。もちろん会場では本の販売もしています。
マンガで出てくるオノミユキご本人に出会え、サインもしてもらえますよ。
(実物はマンガのようにガミガミ怒るおかあちゃんではありませんので、念のため)

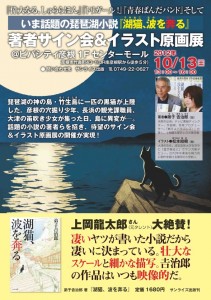
 サンライズ出版
サンライズ出版