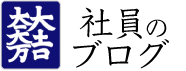B5 168ページ 並製 ISBN978-4-88325-407-1 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年01月 書店発売日:書店発売日:2010年01月25日
1500円+税

「手前味噌」ではあるが、手作りした味噌は本当に美味しい。
3年前に生協で麹を買って作ったところ、家族に好評だったので、東京にいる妹にも送ってあげた。妹は「恐る恐る食べたら、美味しかった」という感想。これ は喜ぶべきか、怒るべきかと少々悩んだ。
去年からは、地元産で賄うべき、麹は花しょうぶ通りの「麹七」さん、大豆は道の駅とか農協で売っている「生産者○○さん」というのを買っている。
16日の土曜日、前日から水に漬けておいた大豆1.5キロを七輪でコトコト炊いたのと、0.5キロは2番目の姉にもらった圧力鍋で炊いて、準備万端。

大豆を水に漬けている容器は我が家では「べに鉢」と言っているのだが、直径が30センチと36センチ位の陶器製で、実に使いやすい。祖母の代には恐 らく味噌も作っていただろうから、たぶんこの「べに鉢」で大豆を水に漬けていたんだろうな?

そして、味噌作りをしようと思い立ったきっかけが、こちらの餅搗き機。たまたま餅米をもらったので、「餅搗き機が欲しい~!!」と言ったら、母が買ってく れたのだが、取説を読むと、味噌作りレシピが書いていたのだ。
コンビニもない田舎に住んでいて、この歳(昭和28年生まれ)で味噌作りと言えば、ふつうは母親から伝授してもらうのだろうが、残念ながら母は都会育ちの ため、そんなことは知らないから、セッセと手作り食品の本を見ながら、作ったのだった。
そうね、聞く人がなくても、本を見ればわかる。
前置きがずいぶん長くなってしまったが、本はそういう意味でとても重要なものなのだ。
ちなみに、『つくってみよう滋賀の味』もずいぶん活用させてもらっている。
最初に作った本2冊が品切れとなったので、2冊の主なレシピを併せて『新装合本 つくってみよう 滋賀の味』を先月刊行しました。
あっ、味噌作りレシピは、この本には掲載されていませんのであしからず。
「手前味噌」ではあるが、手作りした味噌は本当に美味しい。
3年前に生協で麹を買って作ったところ、家族に好評だったので、東京にいる妹にも送ってあげた。妹は「恐る恐る食べたら、美味しかった」という感想。これは喜ぶべきか、怒るべきかと少々悩んだ。
去年からは、地元産で賄うべき、麹は花しょうぶ通りの「麹七」さん、大豆は道の駅とか農協で売っている「生産者○○さん」というのを買っている。
16日の土曜日、前日から水に漬けておいた大豆1.5キロを七輪でコトコト炊いたのと、0.5キロは2番目の姉にもらった圧力鍋で炊いて、準備万端。

大豆を水に漬けている容器は我が家では「べに鉢」と言っているのだが、直径が30センチと36センチ位の陶器製で、実に使いやすい。祖母の代には恐らく味噌も作っていただろうから、たぶんこの「べに鉢」で大豆を水に漬けていたんだろうな?

そして、味噌作りをしようと思い立ったきっかけが、こちらの餅搗き機。たまたま餅米をもらったので、「餅搗き機が欲しい~!!」と言ったら、母が買ってくれたのだが、取説を読むと、味噌作りレシピが書いていたのだ。
コンビニもない田舎に住んでいて、この歳(昭和28年生まれ)で味噌作りと言えば、ふつうは母親から伝授してもらうのだろうが、残念ながら母は都会育ちのため、そんなことは知らないから、セッセと手作り食品の本を見ながら、作ったのだった。
そうね、聞く人がなくても、本を見ればわかる。
前置きがずいぶん長くなってしまったが、本はそういう意味でとても重要なものなのだ。
ちなみに、『つくってみよう滋賀の味』もずいぶん活用させてもらっている。
最初に作った本2冊が品切れとなったので、2冊の主なレシピを併せて『新装合本 つくってみよう滋賀の味』を先月刊行しました。
あっ、味噌作りレシピは、この本には掲載されていませんのであしからず。
古代史最大の謎・邪馬台国論争に一 石を投じる書を編集中です。
纒向(まきむく)遺跡報道で賑わう「畿内説」、根強い支持者を持つ「九州説」を退け、
滋賀県守山市と栗東市にまたがる「伊勢遺跡」こそ邪馬台国であると説く、
その名も『邪馬台国近江説 纒向遺跡「箸墓=卑弥呼の墓」説への疑問』。
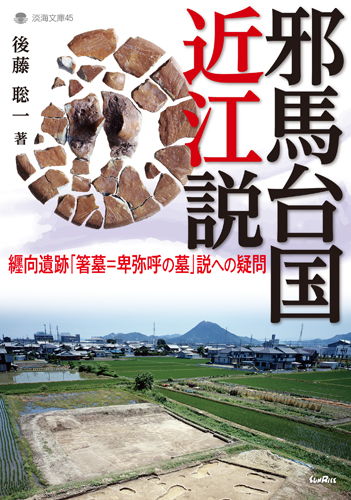
本書「はじめに」で、著者の後藤聡一氏はこう述べています。
私の場合「はじめに物証ありき」からスタートした。まず伊勢遺跡の物的証拠である出土品の多様性、特殊性に注目し、他の遺跡との比較検討を行った 結果、卑弥呼と同時代の遺跡で、これを超えるものはないとの結論に達した。
2月11日(建国記念の日)発行に向けて鋭意進行中。もう少々お待ちください。(Y)
———————————————————————————————————————
■伊勢遺跡
■萌 える日本史講座 卑弥呼は古代の“おひとりさま”
■後藤聡一著『邪馬台国近江説 纒向遺跡「箸 墓=卑弥呼の墓」説へ の疑問』
———————————————————————————————————————
早速ですが、今年もまた大河ドラマネタ。
今夜から始まる「龍馬伝」。井伊直弼役は
松井範雄さんが演じることがすでに決まっており、
滋賀県民としてはどのように演じられるかが気になるところです。
一昨年の「篤姫」で中村梅雀さんが好演した後だけに、
役者さんとしても演じがいがあるのではないでしょうか。
ほか、個人的に注目しているのは以下の配役です。
岩崎弥太郎:香川照之
山内容堂:近藤正臣
吉田東洋:田中泯
河田小龍:リリー・フランキー
お元:蒼井優
特に蒼井優さんは大河初出演とのことで、
来年の「江~姫たちの戦国~」キャスト予想の
下馬評にまた影響を与えるかもしれませんから、
NHKによる正式発表までまた騒がしくなりそうです。
ちなみに龍馬が暗殺される場所は京の「近江屋」で、
龍馬とともに絶命する中岡慎太郎役は上川隆也さん。
「功名が辻」の山内一豊役といい、滋賀にご縁があるようで。(Y)
[前回からのつづき]
前回分で戦前期最大のエピソードを「琵琶湖」にからめてまとめられたのはよいのだが、この『中井正一伝説』の本文と年譜には、私が知っている出来事が抜けている。1937年のたぶん7月、中井たち『土曜日』の同人とその家族は、琵琶湖周辺へ出かけて『「土曜日」の一周年ピクニック』という映画を撮影しているのである。
1995年(平成7)10月3~9日、山形市内を会場に開催された「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の4日目、6日(金)午後6時30分から山形中央公民館大会議室でこの映画が上映された。上映前には、監督を務めた能勢克男の息子・協氏(美術家)によるお話もあった。
この映画祭で上映された作品は278本、6つの上映会場で平行して上映されていくのですべてを観ることは不可能。私は1泊2日で6日と7日に14本観ただけ。最初に観はじめた『サタンタンゴ』(ハンガリー)が450分(7時間30分!)もあり、面白かったのだが、さすがにこれでは1日1本で終わってしまいまずいというので、第1部が終了して休憩になったところで退席。短編作品ばかりをテーマ別にまとめて上映していた別会場(中央公民館)に移動して、たまたま観ることになったのが、能勢克男監督作品『飛んでいる処女』(7分)と『「土曜日」の一周年ピクニック』(12分)だった。
『飛んでいる処女』の方は、走行する市電の窓から頭上に網の目のように張りめぐらされた架線を撮影したカットは覚えている。琵琶湖疏水による水力発電で動く市電は当時の科学技術の象徴なのだろうし、溌剌とした女性車掌の姿=女性の社会進出と合わせて先端風俗に関心をいだく中井の好みも反映されているように思う。テーマは決まっているわけで、まとまりはこちらの方がよい。
それに対して『「土曜日」の一周年ピクニック』はタイトルどおり、内輪向けのホームムービーである。同人とその家族が参加した公園へのピクニック、原っぱでのダンス、琵琶湖でのヨットクルージングのようすを撮影して編集したもので、「土よう日」と書かれた旗がはためくカットが何度もインサートされ、見ていて少し恥ずかしかった。同映画祭のパンフレットによれば、ベレー帽をかぶった中井正一も写っていたそうだが記憶にはない。夕暮れ近く陽が傾いて、デッキにいる男性2人の背後で湖面が輝くところだけがきれいで記憶に残った。
上映された大会議室はイスなしのカーペット敷き(畳だったか?)、ビニール袋に靴を入れて座って(左右に余裕があれば寝ころんで)観る形で、観客は 40~50人だったか。私の前に、平日だというのに母親と来ていた少女がバレエを習っているのだろう、広げた足の間に上半身を下ろして床につける柔軟体操を作品と作品の間の待ち時間になるとやっていたのを覚えている。提供者・能勢協氏の話の内容は何も覚えていない。治安維持法違反での検挙時にフィルムが没収されたことなどが中心だったのではないかと思う。ピクニックの撮影地が琵琶湖だという話は出なかったはずで、私は後でパンフレットによって知った。とするとダンスを踊った原っぱのある公園は、長等公園(大津市)ではないかと思うのだが…。
どうしても知りたいというわけではないけれど、10年余りにわたってもやもやとしつづけている疑問にようやく回答が…と、期待して図書館で本を手に取ったのだが、そうはならなかったわけである。
11月のことだが、京都を拠点に活動しているバンド、モーモールルギャバンのファーストアルバム『野口、久津川で爆死』を買ったら、1曲目が「琵琶湖とメガネと君」という曲だった。メロディは全10曲の中で一番今のロックバンド風、キャッチーな曲にあたるのだろうが、歌詞はというと、岸辺にしゃがんで水面を眺めながら、彼女の視力を奪おうとたくらむ男の妄想。アルバム最後の「サイケな恋人」はさらに過激に女の子目線で彼氏を「あなたはゴミ 消えればいい」と歌うアンチ・ラブソング。
メンバーは群馬出身2人、奈良出身1人とのことだが、京都の住人の創作物に現れた琵琶湖ということで、12月に読んだ本とで、二つまとめて紹介しておく。
彦根市立図書館の新刊コーナーで見つけたのは、馬場俊明著『中井正一伝説─二十一の肖像による誘惑─』(ポット出版)。その後、アマゾンで購入(3500円+税)。美学者・中井正一の、日本初の帝王切開手術とされる特異な生誕の経緯から、戦後、国立国会図書館の副館長として法整備等に活躍し、52歳の若さで没するまでの生涯をたどった454ページの労作。
広島県尾道に生まれた中井は、広島県高等師範学校付属中学校を卒業して、1917年(大正7)、京都第三高等学校に入学。ボート部に入部。三高ボート部といえば、「琵琶湖周航の歌」を生んだところ。中井と琵琶湖のつながりが生まれる。
1922年(大正11)、京都帝国大学文学部哲学科に入学。やはり、ボート部に入部。
翌年と翌々年には文学部のコックス(舵手)として、瀬田川で行われた同大水上大会に出場。琵琶湖畔にあったダンスホールにも出入りしたモダンボーイ。
1926年、大学院に進み、結婚。
1930年(昭和5)、『京都帝大新聞』に「スポーツの美的要素」を寄稿。
これは、長田弘編『中井正一評論集』(岩波文庫)に収められた主要論文のうちで最初期のもの。
「(ボート競技のクルーが)敵艇の接近を一櫂一櫂とのがれゆく心境は、その進行する一艇に自分が乗れる意味で、蓋然より必然へと自らの艇を引きずる意味において、この外的現象は彼等クリュー(クルーのこと)の内面判断構造を具象化する。内なるものを外に見出す意味で深い象徴である」
といった、中井自身が瀬田川や琵琶湖の上で経験したことから導き出されたスポーツに対する考察は、その後も映画やジャズ、探偵小説、フォード車の最新モデルを率先して対象としていった彼にふさわしいものであるだろう。
1932年、貴志康一らと前衛映画を制作。巻末年譜によると、同年7月、友人や息子とともに近江舞子(大津市)で水泳をしている。
1935年(昭和10)2月、同人雑誌『世界文化』を創刊。
1936年(昭和11)7月、能勢克男(京都在住の弁護士)らと月2回刊の文化新聞『土曜日』を創刊。
1937年11月、治安維持法違反で中井ら4名が検挙(翌年6月に能勢ら2名も)。
内務省警保局の記録によると、「(これらの雑誌・新聞は)表面合法を装うも其の真目的は所謂人民戦線戦術に依る共産主義社会の実現を企図しつゝ活動し居るものなること」が判明したので検挙したとなっている。
1938年、警察の取り調べ。
取り調べ検事が、検挙者のうち中井と和田洋一の2人は「どう考えてもマルクス主義者ではないので、起訴したのはまちがいだった」と言ったと後に和田は書いているそうだが、では中井は何主義者だったかといえば、いい意味でのモダニストだろう。
1939年、保釈直前にジフテリアにかかり入院、自宅軟禁(療養)中に、次男4歳が病没。
濡れ衣といってよい罪で自宅を留守にしていた間にさらなる不幸におそわれた中井は、釈放され保護観察生活を送るようになると、琵琶湖へおもむいた。子供を連れてヨットで琵琶湖に出ては、「遠くにかすむ近江富士(滋賀県野洲市の三上山。標高432m)に向かって、いつも『バカヤロー』と叫んでいた」と書かれている。
[小ネタ二つのつもりで書き始めたのだが、片方が予想外に長くなった。次回にもつづく]
新年あけましておめでとうございます。
新年早々、意味シンなタイトルにしてみました。
女性専用車両と出生率低下について論じる
つもりはではなく、よくあるパソコンでの誤変換のお話。
有名なのは「パン作った」→「パンツ食った」でしょうか。
以前「三姉妹」→「産しまい」の記事で一部ダメ出しをいただきましたが、
懲りずに変換ネタでいこうと思ったのは、現在再校中の書籍に出てくる
「伊勢遺跡」を私のパソコンで一括変換すると「異性席」って、おい!
伊勢遺跡とは、滋賀県守山市と栗東市にまたがって
東西約700m、南北約450mの楕円形状に広がっている
弥生時代後期の集落遺跡。ここがなんと邪馬台国だったのではないか?
というのが本書の内容で、詳しくはおいおい紹介していきます。
本年もくだらないネタを交えつつ、
マジメに更新していきますので、よろしくお願い申し上げます。(Y)