
Archive for 2010
2010年 4月 19日
今年はアユが豊漁
近くのスーパーに獲れたてのコアユが並んでいたので、思わず買いました。
寒い日が続いていますが、山椒の葉っぱは毎年より生育がよく、早速コアユを炊きました。

コアユは足が早いから、とにかく買ってきたらすぐ炊くこと。
醤油、砂糖、酒を鍋に入れて火にかけ、沸騰してきたら、コアユを一匹ずつ
煮立ったところへ放り込み、山椒の葉を上にたっぷり載せて、落し蓋して
弱火で炊きました。臭みもなく、やわらかく炊けてホッとひと安心。
分量を知りたい方は『つくってみよう滋賀の味』に 載っているので、
ぜひお買い求めください。
ついでに昆布の佃煮がなくなったので羅臼昆布を買ったのですが、
今年も品薄らしく200グラムで3000円ってメチャ高です。
去年までは、ネットで100グラム1000円の傷2等のを買っていたから、
5割アップです。

とりあえず、鋏で切って、鍋に入れ、醤油と酢を少々入れて一晩置いておきます。
途中数回、鍋をゆすって、昆布に醤油がまんべんなく行き渡るようにし、明日の晩、
炭火で4時間ほどじっくり炊き上げることにします。
2010年 4月 1日
第22回大近江展にご来場ありがとうございました
24日から東京日本橋で始まった第22回大近江展は、開花宣言後にやってきた真冬並みの気候が連日続き、主催者は気が気ではありませんでした。ところが、熱烈な近江ファンの多くのご来場をいただき、無事29日に閉幕しました。
お足もとの悪い中、ご来場いただきました皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
例年より1カ月遅れの会期、しかも年度末、さらには寒い毎日という悪条件でありましたが、会場は熱気ムンムン。近江の工芸品、名産品が多く出店されて、好評を博しました。
そして27日には、今や全国的なビッグタレント「ひこにゃん」がお出ましいただき、熱気は最高潮。
初日、前日にご来場いただいた文部科学大臣や知事以上の護衛がつき、追いかけるカメラを遮るようにすごいダッシュで会場を素早く駆け抜いたのでした。
4年前、誕生した時には、ほとんど認知度がなく、振り返ってももらえなかったものの、愛嬌をふりまくけなげな姿が思い出されます。本当に偉くなったものです。
来年は新年より、近江戦国の姫たちを主人公とした大河ドラマが始まります。おそらく近江展のテーマは、江様中心になるでしょう。どうぞ来年も大近江展をご期待ください。
四六判 202ページ 並製 ISBN978-4-88325-412-5 品切(絶版)
奥付の初版発行年月:2010年03月 書店発売日:書店発売日:2010年04月01日
1800円+税
2010年 3月 30日
『日吉山王祭』山口幸次写真展開催
比叡山の麓、日吉大社のある坂本に生まれ、坂本歴史文化保存会会長でもある山口幸次さんの写真展が開催されます。
と き 2010年4月3日(土)~19日(月)
9時30分~20時
ところ アルセ平和堂坂本店2階
大津市坂本7丁目24-1
電話077-578-3111
4月14日の船渡御で有名な日吉山王祭。そのお祭りの全貌を1冊にまとめた『日吉山王祭』発刊記念の写真展です。『日吉山王祭』は坂本店3階書籍売場で販売しています。
2010年 3月 30日
鳥居本合羽の歴史
馬場弥五郎の工夫で、良質の合羽製造を行ってきた鳥居本合羽は、戦後まで、鳥居本の重要な産業でした。元文、寛保年間(1736~1742)の製造業者数は10戸を数え、寛延・宝暦(1749~1763)になると13戸、文化・文政(1804~1829)には15戸に増加したとされます。店頭販売の他、行商、諸候の用達などもおこない、販路の開拓に努めています。維新以降、明治20 年(1887)には同業組合を結成し、時代に即応した規約を設けて事業の振興に努力してきました。
彦根市史では、「大正初期には同業者20戸従業員数200人を超えるに至った」と記載されていますが、明治20年に設立された日本油脂加工製造組合の資料から、昭和初期の業者数や従業員数を鑑みると従業員が200名に登ったという事実は信じられません。最盛期でも40~50名の従業員で、多くの合羽製造業者は家内従事者を主とした形態であったと考えられます。原材料の協同購入や品質管理などを行ってきた組合も、戦争中の物資統制によって、昭和17年には解散し、日本油紙工業会近畿支部として丸田屋ら数名が加盟しています。
文化2年(1805)に坂田屋から分家した丸田屋の生産高は鳥居本での首位の座を確保していましたが、昭和31年の火災後には生産が中止となり、丸田屋に次いで昭和32年には住田屋も廃業し、鳥居本合羽の生産は終焉したようです。昔ながらの合羽の看板を掲げる松屋は、文政8年(1825)に丸田屋から分家し、昭和の時代には縄などの製造販売に転じましたが、作業所をはじめ、詳細な家屋配置図が彦根市の調査報告書や上田道三氏の記録画に残りました。
2010年 3月 30日
街道を行き交った人々
<皇女の下向道>
江戸時代、東西を結ぶ幹線として重要な東海道や中山道は、参勤交代の行列など多くの人々が行き交いましたが、東海道と違って大きな川を越えることがない中山道は川留めに遭うことがなく計画的な旅ができるメリットがあり、とくに江戸への姫君の婚礼の下向は中山道が利用されました。とりわけ中山道史上例を見ない大行列は、孝明天皇の妹和宮親子内親王の徳川家茂への輿入れで、総勢3万人に及ぶ大規模なものでした。各宿場では、幕府の役人によって事前に綿密な見分が行われ、人足の準備や建物の修復や新築、道路の改修などその対応には莫大な費用を要しています。
<朝鮮通信使>
百々の道標から彦根城下に入る道は彦根道と呼ばれますが、一方、朝鮮人街道とも呼ばれます。朝鮮通信使一行は、大坂から淀川をさかのぼって、淀に上陸し、京都から大津で昼食、草津から中山道に入り、守山で宿泊し、野洲町小篠原から朝鮮人街道を利用しました。守山で宿泊後は近江八幡で休息し、彦根宗安寺で宿泊後、鳥居本からふたたび中山道、美濃路を経て江戸にむかいました。前日宗安寺を出発した一行は翌日に摺針峠の望湖堂で休憩しています。
<商いの道>
江戸時代中期から全国を商圏に、近江商人の活躍がはじまります。日野や近江八幡、五個荘などから発祥した近江商人は、御代参街道や中山道を通り、江戸や関東・東北をめざして行商の旅にでかけました。街道沿いで生産された野洲晒や高宮上布は近江商人の重要な商品となり、そして、各地からまた中山道などの街道を通じて近江や上方に持ち帰る「諸国産物回し」は近江商人独特の商法でした。近江商人が全国で活躍した背景には、近江を通過していた東海道や中山道の存在が大きく影響していました。
<文人たちと鳥居本宿>
鳥居本宿には歴史上著名な人物が逗留したことは、現存する絵や書で知ることができます。有名な芭蕉については別途記載しますが、江戸中期の画家で、円山派の祖である円山応挙(1733~17951)の鶴の画が有川家に残り、国学者本居宣長の書簡は岩根家に残ります。多くの人が鳥居本に逗留したようです。

原八幡神社境内の芭蕉昼寝塚(左)と祇川の句を記した白髪塚
芭蕉と森川許六の終の住処「五老井の跡」
「行く春を近江に人と惜しみける」と詠んだ俳聖松尾芭蕉は、近江に縁が深く滋賀県内の各地に芭蕉に関わる話が残ります。原八幡神社の境内には、「ひるかほに 昼ねせうもの床のやま はせを」という芭蕉の句碑が立ち、昼寝塚と呼ばれています。この芭蕉の句は森川許六著の『韻塞』に収録されたものです。芭蕉が東武吟行の際に美濃路あたりから、彦根城下、明照寺の住職李由のあてた手紙の中に詠まれたもので「美濃路を歩いていると昼顔があちこちに咲いています。李由さんの近くには床の山がありますが、私も昼寝したいものです」という意味があります。
李由や許六は芭蕉の弟子の中でもとりわけ優れた俳人で、ことに許六は芭蕉十哲の一人で、俳句のほかに画をよくしたことで知られ、芭蕉に絵を教えたといわれます。原東山霊園事務所の横には、許六が晩年を過ごした住居跡を示す「五老井跡」の井戸が残り、傍に「水筋を尋ねてみれば柳かな」という許六の句碑が建っています。この句碑は許六と同じ彦根藩士であった谷鉄臣の筆により明治30年頃に建てられたということです。
A5判 128ページ 並製 ISBN978-4-88325-414-9 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年03月 書店発売日:書店発売日:2010年03月30日
2400円+税
2010年 3月 26日
「大近江展」3月29日まで開催です
日本橋高島屋で開催中の「大近江展」。
3月27日(土)はひこにゃんが会場に来ます。
2007年の「近江展」から数えてこれで4回目。
ひこにゃん誕生の謂われを絵本にしたのが『ひこねのよいにゃんこのおはなし』でした。
今回、大近江展ではこの「ミニ絵本とフィンガーパペット」をセットにした商品2,100円を特別特価1,260円で限定100個販売していますので、お見逃しなく。
また、24日にできたばかりの『岐阜の山城ベスト50を歩く』は、近江のお隣り県ということで、ひと足早く会場でも販売しています。書店には3月末日頃並ぶ予定です。


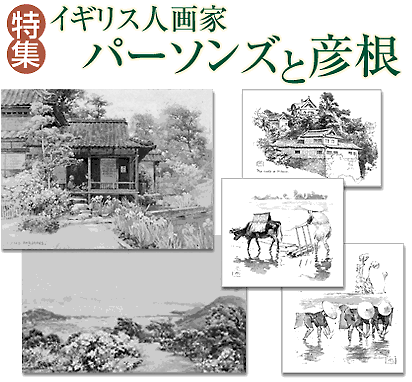

 サンライズ出版
サンライズ出版