
Archive for 2010
A5判 123ページ 並製 ISBN978-4-88325-417-0 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年04月 書店発売日:書店発売日:2010年05月10日
1800円+税
A5判 64ページ 並製 ISBN978-4-88325-418-7 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年04月 書店発売日:書店発売日:2010年05月07日
1000円+税
2010年 4月 30日
鳥居本合羽

天保3年創業、戦前まで合羽を製造していた「合羽所 木綿屋」
鳥居本宿で合羽製造が始まったのは、享保5年(1720)馬場弥五郎の創業であると伝わります。若くして大坂に奉公にでた弥五郎は、当時、需要に追いついていない合羽製造の改革を決意し、奉公先の坂田屋の屋号を譲り受けて鳥居本宿で開業し、新しく菜種油を使用していた合羽製造に柿渋を用いることを奨励しましたので、一躍、鳥居本宿で雨具の名声はたかまりました。柿渋は、保温性と防水防湿性に富み、雨の多い木曽路に向かう旅人は、こぞって鳥居本宿場で雨具としての合羽を求めるようになりました。
鳥居本合羽が赤いのは、柿渋を塗布するときに紅殻を入れたことによるとされます。赤い合羽はとくに上もので、主に北陸方面に販売されました。江戸時代より雨具として重宝された渋紙や合羽も戦後のビニールやナイロンの出現ですっかりその座を明け渡すこととなり、今では看板のみが産地の歴史を伝えています。
2010年 4月 30日
中山道の始まりと街道の整備
中山道の原型とされる古代近江の東山道は、7世紀の中頃に駅制の整備にともない建設されたと考えられ、『延喜式』では、東から横川、鳥籠、清水、篠原、勢多に駅が置かれたことが確認されています。鎌倉幕府を開いた源頼朝は文治元年(1185)に駅制を制定し、京都鎌倉間を東海道としたことで、近江の東山道の利用も活発になりました。そして関ヶ原の合戦に勝利した徳川家康は京都と江戸を結ぶ重要なルートとして東海道・中山道の整備に着手しました。当時中山道は「中仙道」としるされましたが、享保元年(1716)に新井白石の進言で「中山道」を正式表記としましたが、その後も「中仙道」は使用されています。
慶長7年(1602)7月に幕府の命により奈良屋市右衛門と樽屋三四郎が、中山道の宿々に駄賃銭を定め、小野村を伝馬継所として通告しましたが、翌慶長8年に宿場は小野村から旧鳥に変更され、上矢倉村、西法寺村、百々村の3ヶ村が加わり鳥居本宿が構成され、本陣1軒、脇本陣2軒、問屋場1軒が定められ、問屋の前には高札場が設置されました。
天保年間(1830~44)の宿場の概要を示す宿村大概帳によると、鳥居本宿の経済状況は、鳥居本村の115石余のほか、西法寺村1112石余、百々村 207石余、上矢倉村237石余であり、下矢倉村境より小野村境まで13町余の長さがありました。また、総人口は1448人、家数は293軒でそのうち、旅籠屋が大小合せて35軒。宿場の役人として、年寄5人、庄屋役5人、横目役4人、馬差2人、人足肝煎2人、人足指4人が配置されていました。通常は、問屋1人ならびに馬指・人足肝煎・人足指各1人の役人が出勤し業務に従事していました。
宿駅制度を定めた幕府は、江戸日本橋を起点に、旅人や通行の距離の目安として、街道の両側に松や榎木などを1里ごと植えた一里塚を築きましたが、上図中央には鳥居本宿にも一里塚があったことを示しています。
2010年 4月 30日
佐和山城の遺構

佐和山山頂から鳥居本町、遠くに伊吹山が見える
大手門跡から近江鉄道の線路をくぐり、小野川に沿ってさらに進んだ、山沿いの三の丸付近には、殿町谷など城下町を示す小字名が残り、内町老人会によって登山道の標識がたてられています。ここからまっすぐに登ると通称「龍潭寺越え」とよばれる交差点となり、さらに登り尾根の切り通しに出て、西の丸を経て坂を登りつめると本丸に出ます。本丸までは、通常佐和山トンネル彦根側からのハイキングコースをとりますが、鳥居本側からも容易に山頂に出ることができます。
かつて五重塔がそびえていたといわれる頂上からは、遠くに安土山、小谷山が見渡せ、伊吹山も手にとるような距離に望むことができます。本丸跡から少し下ると腰郭跡に2段の石垣が残り、城郭跡が感じられる遺構に出会います。関ヶ原の合戦で壊滅的な破壊を受けたといわれる佐和山城ですが、石垣をはじめ千貫井の存在など随所に遺構を見ることができ、この城郭が当時、重要な役割を持っていたことがよくわかります。
2010年 4月 30日
鳥居本小学校
明治19年11月1日小学校令が実施され、今まで各集落ごとにあった学校が廃止され鳥居本尋常科小学校、鳥居本簡易小学校として開校しました。明治24 年4月1日小学校令が改正され、原、荘厳寺、武奈、男鬼の学校が廃止され、鳥居本全村を通学区域とする鳥居本尋常小学校となりました。明治31年4月には高等科を設置し鳥居本尋常高等小学校と改称。昭和16年4月1日国民学校令により鳥居本国民学校と改称。昭和22年の新教育制度6・3・3制の学制実施により昭和23年4月1日から鳥居本小学校と改称され現在に至っています。


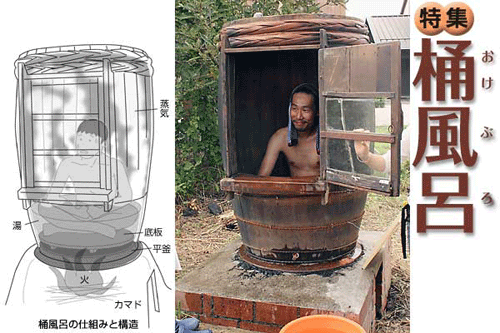



 サンライズ出版
サンライズ出版