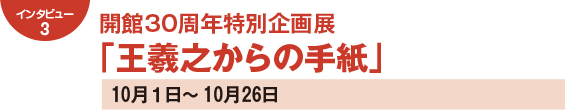
王羲之に加え、宋代の書家3人もそろい踏み
――少し早いのですが、秋に開催の特別企画展「王羲之※8からの手紙」についてご担当の瀨川学芸員にお話をお聞きします。今回、初めて国宝が来るそうですね。
瀨川 はい。重要文化財は何度か展示しているのですが、国宝は初で、王羲之「孔侍中帖」が来ます。
当館のコンセプトが「書の文化にふれる博物館」で、日本習字という書の団体が運営している博物館ですので、30周年を機に原点に立ち返るという意味で企画した展覧会です。王羲之は、書の世界ではとびきり知名度が高い人物ですし。
――名前だけは聞いたことがあります。簡単に言うとどういった人物なのですか。
瀨川 書というものを単なる実用の手段ではなくて、芸術のレベルに引き上げた人と言えるかと思います。
――素人目で見ると、普通の漢字だな、よく見る書と感じるのですが。
瀨川 皆さん、それだけ王羲之を勉強するからなんです。
――全部、基本が王羲之なんですね。
瀨川 そうです。その後の書は、ずっとどこかで王羲之の遺伝子のようなものを受け継いでいるんです。特に唐の初めの頃の皇帝、太宗※9が王羲之の書が大好きで、それを大事にしたので、臣下もみんな皇帝が好きな書を勉強しました。それができないと試験にも通らないような流れになったので、基本に王羲之が置かれて、以後も継承されていったのです。
日本もその頃、例えば空海などが唐に留学して、王羲之風の書を勉強して帰ってくると、優れた書家として知られるようになり、その書風が受け継がれていきました。
――日本で書の名人といえば空海ですから、その源流にあたる王羲之はまさに原点なんですね。ですが、実際に本人が書いた作品は残っていないとか。
瀨川 はい。現在あるものは全部写しで、写したものですら国宝になっています。今回出品する「孔侍中帖」は唐代でも古い、7~8世紀の頃につくられたもので、それが日本に渡り、おそらく正倉院に入っていたというような経緯をたどっています。その流れだけでも非常に歴史的背景を持った史料ということになります。
そもそも本人の肉筆が残っていないので、推測する以外にないのですが、今に伝わる写しの中でも特によく写されていると評価されている作品です。
所蔵している公益財団法人前田育徳会(東京都目黒区)は、加賀藩主前田家に伝わった古美術を保存管理しているところで、石川県立美術館や東京国立博物館で公開されることが多く、滋賀県での公開は初めてです。
――6月になって館のサイトで「緊急告知! この秋、国宝王羲之「孔侍中帖」が来ます!」と発表なさっていました。そのぐらい、すごいことなのですね。
瀨川 王羲之「孔侍中帖」をトップに出していますが、王羲之以外の有名な書家の作品も目玉です。蘇軾※10「行書李白仙詩」(大阪市立美術館所蔵)、黄庭堅※11「李太白憶旧遊詩巻」(藤井斉成会有鄰館)、米芾※12「草書四帖」(大阪市立美術館所蔵)の3点を同時に見ることができます。蘇軾、黄庭堅、米芾の3人は宋の時代を代表する書家です。この3点の作品がそろい踏みするというのは、なかなかないことです。
そのうち2点は大阪市立美術館、1点は藤井有鄰館の所蔵で、滋賀県出身の阿部房次郎と藤井善助のコレクションによるものですから、これらを東近江市で展示する意義というのもあります。
黄庭堅の作品をお借りする藤井有鄰館は、実はなかなか貸していただけません。駄目もとで依頼したのですが、当館のすぐ北に藤井善助邸跡と彦四郎邸がある、つまり創設者の出身地のすぐ近くにあって、関西中国書画コレクション研究会にも参加している当館だったらということで、唐代の「西域出土文書」と一緒にお貸しいただけることになりました。
――最初の新館10周年のお話で出てきた研究会のネットワークが役立ったわけですね。
瀨川 そうです。もう一つの重要文化財として出品される「李柏尺牘稿」(龍谷大学図書館蔵)は、大谷探検隊という本願寺の大谷光瑞が組織した探検隊が、シルクロードでたまたま発見したという、王羲之と同時代の肉筆史料です。
※8 王羲之 (307~365)中国、東晋の書家。楷書・行書・草書を芸術的に完成させ、「書聖」と称される。
※9 太宗 (598~649)中国、唐の第2代皇帝、李世民。官制を整え、均田制・租庸調制・科挙制などを確立した名君とされる。
※10 蘇軾 (1037~1101)中国、北宋の政治家・文学者。宰相となった王安石の新法に反対して左遷され、諸州の地方官を歴任。
※11 黄庭堅 (1045~1105)中国、北宋の詩人・書家。蘇軾の門下の蘇門四学士の一人。後世の江西詩派の祖とされる。
※12 米芾 (1051~1107)中国、北宋の書家・画家。書においては、以上の3人と蔡襄で「宋の四大家」と称される。
自然な書きぶりを時空を超えて感じていただきたい
――全体のテーマとしては、自然な書きぶりが垣間見られる下書き(草稿)や特定の相手に向けたプライベートな書を集められたそうですが。
瀨川 作品としてカチッとつくったものというより、自由闊達に書かれたものを中心にしています。不特定多数の人に見てもらうために書いたのではなく、個人宛てのようなプライベートな作品や、日常で書かれたものを集めています。「見せてやるぞ」という感じで肩に力が入ったようなものとは、少し趣の違うものをご覧いただけます。
清代の比較的新しい作品は当館のテリトリーにあたるので館蔵品を出しますが、「冊」と呼ぶ本のような形態になっているものなど、ご覧いただく機会の少ない品もふくまれています。
――その手紙の内容にあたる部分も解説はあるのですか。
瀨川 字起こししたものは図録に入れるつもりですが、あくまで「書」ですので、内容から見てしまうと、書かれている字面に神経が行かなくなってしまいます。まずは素直に筆の運びを目で追ってもらうほうがよいと思います。
――確かにそうですが、それはある程度素養がある人にしか難しいのでは。
瀨川 「見方」がわからないと感じて、最初から書というものにアレルギーを持っている方もあると思います。私自身がそもそも書の出身ではなく、中国史の研究から入っていますので、その気持ちもよくわかるのですが。
今から1000年以上前に生きていた人間がわれわれと同じように手を動かして書いたものですから、それを時空を超えて感じ取る行為に、書道の経験がない方も挑戦していただければと思います。
――本日は興味深いお話をありがとうございました。 (2025.6.27)
編集後記
観峰館の開館までの経緯などについては、開館20周年の時に取材した本誌117号で古橋学芸員にお話しいただいていますので、右下のQRコードからバックナンバーをご覧ください。もともとは何の縁もなかった旧五個荘町の現在地のすぐ近くに、日本を代表する中国書画コレクターの一人だった藤井善助の生地があったのは、おもしろい縁です。藤井善助といえば、大ヒット中の映画『国宝』のロケ地として知名度の上がった旧琵琶湖ホテル(現、びわ湖大津館)の取締役会長も務めています。(キ)


 サンライズ出版
サンライズ出版