
Archive for 2010
2010年 10月 12日
白洲正子「神と仏、自然と祈り」展
2010年 10月 11日
滋賀県は地味で良い?
ようやく『近江の祈りと美』の印刷も終わり、あとは製本を待つばかりになり、本日は久々に近くの山を散策し、自生の紫蘇の実を採ってきた。
ところで滋賀県は国宝・重要文化財の仏像が全国で3番目に多いというのにもかかわらず、どうもそのことが全国に浸透していないのではないだろうか?
2007年に講談社が『週刊 日本の仏像』全50巻を出したが、奈良、京都、奈良、京都の繰り返しで、滋賀県と言えば、15号「湖北、湖東の観音めぐり」と27号「延暦寺千手観音と比叡山」の2巻のみ。あまりにも露出度が少ないというか、知られていない。
まあ、観光寺院が多いわけではなく、拝観のときは、地元の寺世話さんに電話をして、お堂を開けてもらうというところも多いから週刊○○で派手にできないという理由はわからなくもない。
ということは同じ講談社が発刊している『原寸大 日本の仏像』も奈良編と京都編の次は、たぶん出ないであろう。
そんなわけもあり、このままだと滋賀県の仏像の本は絶対できないままになってしまうーっ!! といういわば危機的意識もあり、今回滋賀県の仏像をまとめた本を作ることになったのだ。
ずっと作りたいという思いはあったが、著者の寿福さんと高梨さんにお願いしたのは昨年12月、なんとか来週出来上がる。
タイトルにはあえて仏像とか彫刻という名前を入れず、装丁もきわめてシンプル。制作途中で、ケースはカラーにしようと変更したものの、表紙は文字のみというあえて「地味」にした。
派手でなくても良い。でも多くの人に近江のほとけさまを知ってほしい。
2010年 10月 6日
連日のイベント終了
10月2日岡崎市で開催したシンポジウム、200名以上のご来場をいただきありがとうございました。
県外からのご参加も多く、盛会でした。愛知城郭研究会、岡崎市教育委員会の皆さまに御礼申し上げます。
翌3日は「鳥居本宿場まつり」。お天気が危ぶまれたものの、4時頃までなんとか持ちこたえました。喫茶、食事処に加え、一般公開の民家も増えました。我が家の前のヴォーリズさんのお家の前は、ひっきりなしに、イベントが行われていました。
普段は静かな中山道ですが、各地から多くの方にお越しいただき、江戸時代の面影のこる町歩きを楽しんでいただきました。
さて、次の土曜日は伊吹山の麓、上平寺「戦国のゆうべ」で本の販売をします。
2010年 10月 1日
仏像ってむずかしい3
今回『近江の祈りと美』を作るにあたり、とても悩ましかったのは、仏像の背丈です。
像高=頭から足先
総高=全体の高さ
座高=半跏像のときの頭からお尻
確かこういう区分だったんですね。
でも、像高が本によってマチマチなのです。誤植ということもあるけど、調べていくうちにどうやらそうでないような……。で、聞いてみると、まず、重要文化財として登録した時点での身長(像高)と、後で測ったときの身長が違うのです。
私たちが身長を測るときは、身長計に乗って測るけど、仏像の場合は身長計を持ってきて、それに乗っていただくわけではなく、たぶん金属製のメジャーかなんかで測るんでしょうね(実はどうやって測るかを高梨先生に聞きそびれてたわ)。だから、測る度にちょっとした誤差が、生じるらしいです。
それとともに、昔に文化財指定だった仏像は尺貫法だったので、それをセンチに換算すると誤差が出てきているということもあるようです。
2010年 9月 29日
仏像ってむずかしい2
以前、写真を裏焼きして印刷したことがあり、今回もそれだけはとても注意していたのですが、校正のときに発見し、ヒヤッとしました。
そこで、裏焼き防止策について、まず、ポジフィルムの左にギサギザがあるから、それと確認すること。
でも、たまにデュープしたものがさかさまになっていたということてもあったので、オリジナルでない場合は要注意です。
次に、仏像が薄い衣をまとっていて、これを天衣というのですが、天衣は左肩にかけておられるので、それに注目します。後は、既刊図録を見ながらチェックしました。
三尊像などでは、右左が決まっているかと思いきや、逆の場合もありました。たとえば不動明王さんの右にはセイタカ童子君で左はコンガラ童子ちゃんが一般的みたいなのですが、逆の場合もあります。一番悩ましかったのは、三尊集合写真がなくて、一枚撮りのときです。このときは、直接お寺に電話をして確認しました。
2010年 9月 28日
とりいもと宿場まつり開催
中山道鳥居本界隈が日増しに、赤色に染まってきた。街道沿いの民家は、それぞれが赤い布で装飾をほどこし、「三成の佐和山城」ののぼりの中に赤色の「とりいもと宿場まつり」ののぼりが鮮やかだ。本年で3回目となる宿場のお祭り、本年もテーマは戦国。
なんといっても三成さんの居城があった佐和山城下町の一画にある鳥居本では、この時代を重視したい。
当日は、朝から佐和山城に上る企画があり、午後には、織豊城郭研究の第一人者の中井均さんの講演もある。
新しいメニューがそろった出店も楽しみ、民家の開放も嬉しい。それぞれの個性が光る手作りイベントにはあたたかさがいっぱい。どうぞお越しください。
サンライズの書籍の販売も行います。
詳しくは詳しくはチラシをご覧ください。
2010年 9月 28日
仏像ってむずかしい1
ようやく、校正が終了しました。来月19日に発売の『近江の祈りと美』。
内容はというと、近江の仏像、神像を収録した本で、図録風に280頁がカラーで、後半は「近江の彫像」という本論、そして滋賀県におられる国宝・重要文化財・県指定文化財の彫刻一覧を掲載します。
さて、仏像の本を作りたいと常々思っていたものの、結構難しいことがいっぱいでした。
まずはその1。
仏像のお名前、実は同名がいっぱいおられるということです。
一般には「素材」「種別」「立っているか、座っているか」というのでお名前が決まります。
たとえば「木造十一面観音立像」「銅造如意輪半跏思惟像」「木造大日如来坐像」というふうに
だいたい三つのパターンの組み合わせなのですね。
そこに、その仏像の所属するお寺の名前をつければ、どこの家の花子さんとか太郎君ということでわかるかといえば、おっとどっこい、同じお寺に十一面さんや阿弥陀さんがいっぱいおられるわけでして、つまり同姓同名のお方が同居しておられます。
そこで、次に年上か年下か、つまり製作された時代で区別することになり、お名前の後ろに○○時代とつけます。でももっと大変なのは、大きなお寺だと、同時代に造られた同姓同名さんがおられて、時代別では足りず、今度は昔はお寺のどこに住んでおられたか(○○寺旧蔵)とか、像の底をひっくり返して身体検査をすると、お腹あたりに何年に像を造ったとか、願い主は誰々とか、製作者の名前が書かれていたりするので、それを頼りに(○○年銘)とか(○○作)というふうに見分けをつけるのです。
10年ほど前にあるお寺のリーフレットを作成したとき、重要文化財の十一面さんが2人一度に登録されておられていました。2人と書きましたけど、仏像は人間ではないので2人というのは間違いで、躯(く)と言います。だからこの場合も2躯おられました。ご住職も「さてどちらだったやろう」と写真を取り出して本人と見比べておられました。この十一面さんは背丈も同じくらいで平安時代の作。最後は顔で判断しました。あとでわかったのですが、平安時代の作でも、少しお歳を召した風の方が早い年代に造られたものだったようです。
今回の本で、とても似ておられたのは、延暦寺の慈恵大師さん2躯と金剛輪寺と常照寺の阿弥陀如来さんです。
不思議なもので、仕事をしているうちに少しずつ判別できるようになりましたが、できれば「十一面1号、十一面2号」というように名前をつけてほしかったと思ったものでした。
2010年 9月 23日
仏像の本がもうすぐできます。
読者からよく「仏像の本」はありますか?とお問い合わせをいただいていました。既刊本では『近江観音の道』や『近江湖北の山岳信仰』などがあるものの、滋賀県の仏像を集大成した本はちょっとやそっとで作れるはずがない。でも、いつか作りたいと思っていました。
1930年に創業したサンライズは今年80年を迎え、昨年秋頃から何か記念になるような本を作ろうと考えていたこともあり、作るのなら今かも…ということで、清水の舞台を飛び降りる気持ちで取り組んだのが今回の『近江の祈りと美』です。
遅ればせながら、ようやく予約申し込みのリーフレットができました。リーフレットには掲載尊像一覧も入れておりますので、最寄りの書店でご覧ください。
四六判 256ページ 並製 ISBN978-4-88325-424-8 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年09月 書店発売日:書店発売日:2010年09月20日
1600円+税
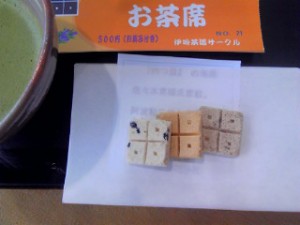

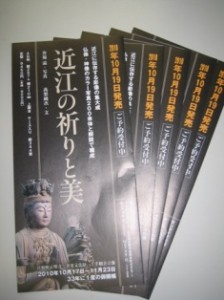

 サンライズ出版
サンライズ出版