
Archive for 2010
170×190 80ページ 上製 ISBN978-4-88325-431-6 在庫あり
奥付の初版発行年月:2010年11月 書店発売日:書店発売日:2010年11月30日
2200円+税
B5 112ページ 並製 ISBN978-4-88325-428-6 品切(絶版)
奥付の初版発行年月:2010年11月 書店発売日:書店発売日:2010年11月17日
1500円+税
2010年 11月 16日
実りの秋は忙しい
私は「アリとキリギリス」のアリのような性格で、秋は保存食作りにいそしんでいます。そこでここ一ヶ月を振り返ってみました。

まずは、母がドーンと買ってきた枝豆。ビールのつまみにしては、ちと多すぎるのではないかということで、残りは茹でて冷凍にしました。枝豆スープやごはんに混ぜたりしたのですが、大豆とひじきの五目煮を作ったとき、ゆでて冷凍にしていた大豆が少なかったので、枝豆も加えたところ、彩りもよくなりました。
10月の中旬はシソの実が獲れます。こちらはサッと茹でて、塩を振り一日重石をします。翌日、上がった水を捨てて、塩をまぶしてビン詰めにすれば一夜漬けに入れたり、ヤキメシのアクセントにしたり、シソ&ちりめんじゃこというのもできます。

さて、こちらは伊吹山の麓、弥高のさつまいもです。
10月の初め、「上平寺のゆうべ」のときに買おうと思っていたのですが、今年は夏のひでりで収穫が少なかったそうで、10月24日の「弥高の収穫祭」に行き、買ってきたものです。実はこの倍ほど買って500円でした。

大学いも、スイートポテト、かりんとうにしたけど、まだしばらく楽しめそうです。
秋といえば、茗荷の梅酢漬けも忘れてはいけないアイテムです。
茗荷は夏に採れるものは結構グサグサしているのですが、秋茗荷は実がしまっているため、こちらを1日塩漬けにしたものを、梅酢に酢を足してビン詰めします。
刻んで、お寿司の具にしたり、ヤキメシに入れたりして使います。
さて、これは初挑戦することになった食用菊です。
編集のk君が坂本へ取材へ行ったときにもらってきた菊です。坂本では食用菊の栽培が盛んで、ちょうど今の時期、菊三昧のお料理が坂本で食べられるのです。
菊の花、約80の花びらだけをむしり取ったのがこれです。鍋に湯を沸かし酢を少々入れたところに洗った菊の花びらをいれて、サッと茹で、水で冷やします。ザルに上げて、軽く水気を切って、酢カップ1と砂糖カップ2/3、塩小さじ2を混ぜた調味液に入れて容器に入れました。
お正月までだとこのままの色が保てると書かれていたけど、果たしてうまくいくかなぁ?
酢のものに入れたり、お寿司にちらしたりできそうです。
 そして、滋賀県の伝統食である日野菜。見たところは大根ぽいですが、かぶらの仲間。日野菜も最近では改良したミニ日野菜を洋食のメニューに使ったりされているらしいですが、やっぱり日野菜は漬物が一番。
そして、滋賀県の伝統食である日野菜。見たところは大根ぽいですが、かぶらの仲間。日野菜も最近では改良したミニ日野菜を洋食のメニューに使ったりされているらしいですが、やっぱり日野菜は漬物が一番。
写真の日野菜は日野町三十坪(ミソツボ)産。日野の八百屋の店先で見かけたので、思わず買ってきました。
さくら漬けは簡単だけど、これは糠漬けに挑戦することにしました。手抜きして半日だけ干した日野菜を糠と塩とザラメを混ぜた混合ぬかに漬けています。今月末頃になれば食べられそうです。果たしてうまく漬かっているかどうか……。
さて、滋賀県の食材を使ったお料理については『つくってみよう滋賀の味』にいろいろレシピがありますので、ご興味のある方は是非どうぞ。
B6判 224ページ 並製 ISBN978-4-88325-430-9 品切
奥付の初版発行年月:2010年11月 書店発売日:書店発売日:2010年11月10日
952円+税
2010年 11月 9日
『近江日野の歴史』第8巻発刊記念講演会
2010年 11月 8日
第9回近江中世城郭琵琶湖一周のろし駅伝
今年も11月23日(火・祝)にのろしが上がります。午前10時、来年の大河ドラマの舞台である小谷城を出発し、時計回りに約50の山城跡からのリレー、サンライズのお膝元、佐和山城は午前11時5分頃とのこと。
同日午後からは佐和山城の麓で「石田三成検定」も実施。詳しくは戦國丸のホームページをご覧ください。ちなみに公式ガイドブックは『三成伝説』です。受験しようと思っている人もそうでない人も是非、お読みください。
2010年 11月 4日
日野町正明寺の御開帳に行きました
文化の日、33年に一度しか拝観できない観音さまにお出会いしました。
正明寺さんは近江西国三十三所の札所で、十年ほど前に仕事の関係もあって、三十三所を廻ったこともあり、とても大きな魚板が印象に残っていたお寺でした。お寺のすぐ近くには鎌倉、室町時代の蔵骨器が見つかった大谷古墓があり、今はこじんまりしたお寺ながら(江戸時代に本堂は再建され、現在は黄檗宗の禅寺)、800年ほど前は、丘陵一帯に伽藍が建っていたのだろうなと、勝手に思いを巡らしてしまいました。
秘仏の三尊像は、お厨子の前まで行くことができ、じっくりと拝ませていただきました。秘仏として普段は開かずのお厨子におられるため、胸の瓔珞は色こそ褪めていますが、残っていました。
正面右手の禅堂は平成12年に落雷で焼失。ちょうど檀家の役員さんが寄り合いをしておられたときだったため、お堂の仏像はなんとか運び出して無事だったと聞きました。当時も禅堂には大日如来さんがおられたのかどうかを聞くのを失念していましたが、あの大日さんもなかなかの美形(こういう表現は不適切か?)で、必見。
ご開帳は11月23日までです。








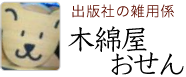
 サンライズ出版
サンライズ出版