2010年 11月 1日
其の四十六 琵琶湖文化館所蔵 両界曼荼羅

右…修理前、左…修理後
琵琶湖文化館が所蔵している仏画の一つに鎌倉時代に製作された両界曼荼羅があります。形あるものがいずれ形を失っていくという道理にしたがい、こうした掛軸などの文化財も徐々に傷んでいきます。この曼荼羅は絵絹に描かれていましたが、絵絹は折れ、絵の具も落ち、公開に支障をきたす状況にまで陥っていました。
平成4年(1992)、琵琶湖文化館ではこの曼荼羅の修理を行うことにしました。大切な文化財ですので、当時県内に発足したばかりの文化財修理工房へ修理をお願いしました。国宝や重要文化財を修理する工房におられた方が独立開業されたもので、当然文化財修理についても相当の実績がある修理技術者でした。
平成4~6年度の3か年をかけて、曼荼羅は無事に修理されました。この修理にあたり、琵琶湖文化館では一つの試みに挑戦しました。それは掛軸の表具です。
掛軸の表具は色とその取り合わせが様々にあることはご承知の方も多いかと思いますが、実は形も色々あります。この曼荼羅では、大きな掛軸にのみ使用されるという表装のスタイルを採用しました。通常の紐で吊りさげるものではなく、表装裂で輪をつくり、そこに棒を通し、取り付けた金具で吊り下げるというものです。
こうしたスタイルの掛軸は京都の東寺に伝わる両界曼荼羅の表装にみられるものですが、全国的にもとても珍しいもので、数えるほどしかありません。琵琶湖文化館の両界曼荼羅はただ修理するだけでなく、途絶えてしまう可能性がある表装の文化までもを同時に後世に伝えようとした事業でもありました。
文化財修理は、今では大変専門的なものとなってしまいました。私も学芸員としての活動の中で、残念な結果となってしまった修理をいくつも見てきました。だからこそ、そうなる前に地域の博物館や教育委員会などに気軽に相談していただけたら、と思っています。
滋賀県立琵琶湖文化館学芸員 井上ひろ美
●井上ひろ美著『淡海文庫 継承される文化財─模写・模造・修理─』(サンライズ出版)が近日発行予定。


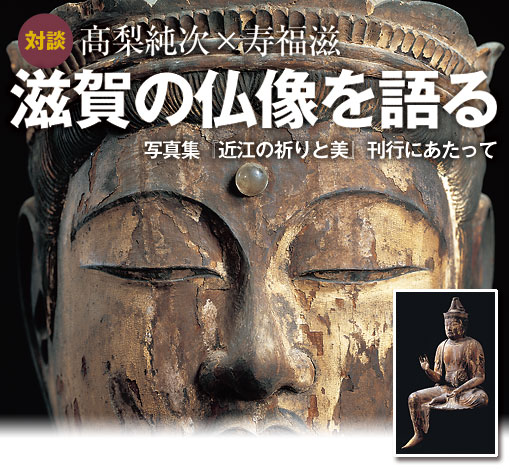


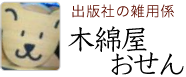
 サンライズ出版
サンライズ出版