2月13日(土)午前11時頃から、NHK総合でバンクーバーオリンピックの開会式を見る。
出ないかな、出ないかなと待っていると、出たよ。k.d.ラング。白のスーツ姿で、レナード・コーエンの「ハレルヤ」を歌う。
ファンなのである。自分の結婚式で流した曲の一つは、彼女の「IN PERFECT DREAMS」だったという、どうでもいい情報も書かせてもらう。1984年から1991年まで最初期7年分のテレビ出演やビデオクリップをまとめたビデオ『HARVEST OF SEVEN YEARS』には、1988年開催のカルガリーオリンピック閉会式に彼女が出演、「TURN ME ROUND」を歌った映像も収められていたので、今回も「もしや」と期待していたのだ。
ファン目線でなくても、圧倒的でしたね(その後のネット上の書き込みを見て)。スタンダード曲を歌うベテラン・シンガーみたいになってるのは物足りないけど。YouTubeには、カルガリーオリンピックでの陽気なパフォーマンス、1995年頃、アルバム『all you can eat』を出して音楽的に一番かっこよかった時期の1曲「You’re OK」のビデオクリップ(なぜか相撲取りに扮する)などもアップされているので、こちらも見ていただきたい。
なので、私のバンクーバーオリンピックは、開会式で半分終了した。後の半分は、顔が好みの川口悠子(フィギュアスケートペア・ロシア代表)。ありがとうカナダ国民。さよならバンクーバー。
そして4月、私の前に再びバンクーバーは現れた。
「バンクーバーオリンピックの放送が毎日にぎやかに行われている。バンクーバーは自分の生まれた都市なので耳懐かしく聞いている」
「私の老妻の家族は、カナダのバンクーバーで暮らしていた。子供の教育は日本でとの両親の計らいから、母親の腹の中にいた老妻は長い船旅で帰国した」
前者は、某退職者団体の会員誌への92歳男性の寄稿、後者は、文芸同人誌へ寄稿された随筆の一節。弊社では、同窓会誌や報告書などの印刷も請け負っており、内校した私が目にすることになったのである。
弊社から『近江商人学入門』を出されている末永国紀さん(同志社大学教授)の新刊『日系カナダ移民の社会史―太平洋を渡った近江商人の末裔たち―』もミネルヴァ書房から出た。
以下は同書カバー折り返しにある紹介文。「1887年、横浜・ヴァンクーヴァー間の太平洋航路開設と相前後して、日本人のカナダへの渡航・移住の歴史は始まる。以来、数千人の人々が新天地を求めて渡加し、『日系カナダ移民』という生き方を選択した。その出身都道府県別人口比の一位は、滋賀県出身者が占めていた。」
もちろん五輪開催を当て込んだ便乗本ではなく、自身が発掘した一次史料をもとに1995年以来書きついでこられた論考6編に加筆をほどこした手堅い歴史書である。1938年の調査ではバンクーバー(本書ではヴァンクーヴァー)は、カナダ在留日本人が最も多い都市(7600人余りのうちの約4割)だった。この調査自体が前年に始まった日中戦争の影響で巻き起こった日本商品ボイコットなどの排日運動に対応するために日本人会が行ったもので、その後、日米開戦後の強制収容所への移動など、日本人移民は苦難の道をたどる。


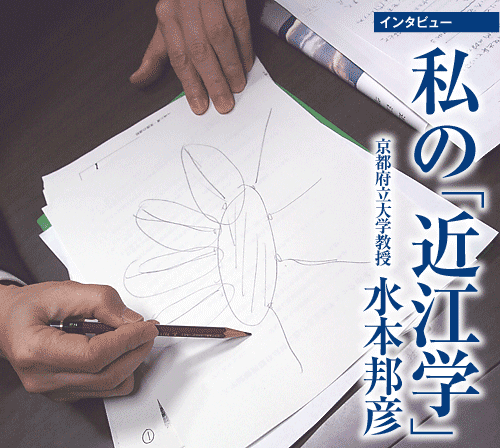


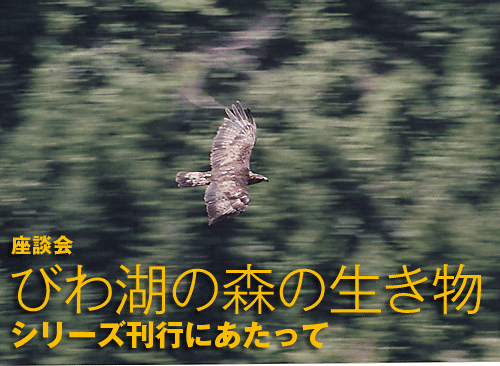
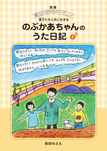

 サンライズ出版
サンライズ出版