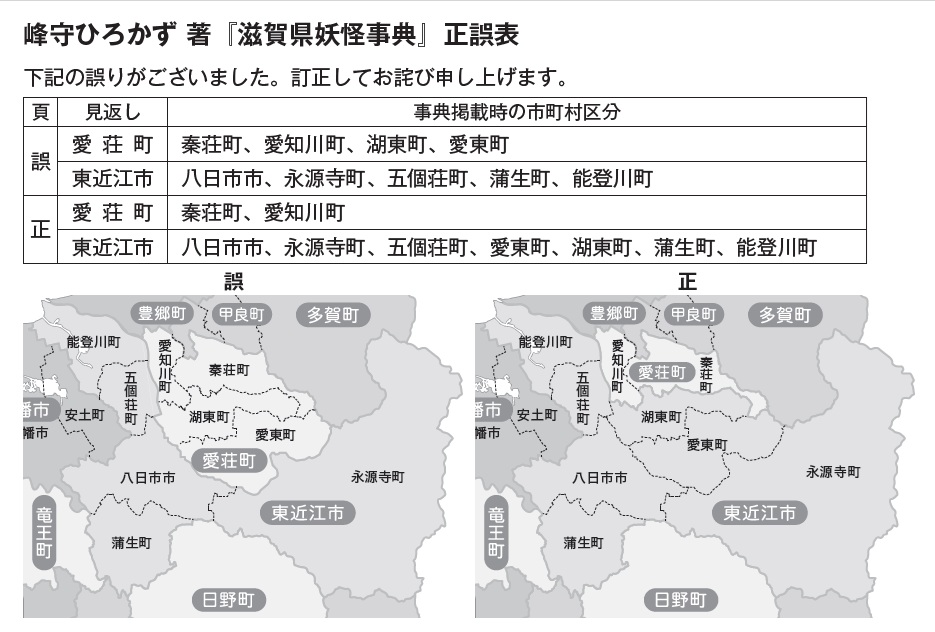昭和17年、戦時学生の日誌
| 判型 | B5判 158ページ 並製 |
|---|---|
| ISBN | 978-4-88325-420-0 |
| 刊行年月日 | 2010年07月17日 |
| 書店発売日 | 2010年07月17日 |
昭和はじめの中学生はこのように生きた―。戦時中の等身大の記録が「のらくろ」ばりの挿絵とともに今よみがえる!2011年ジャグラ作品展経済産業大臣賞受賞。
廠営訓練、麦刈手伝い、実包射撃、連合演習…。戦時中の学生はいかに過ごしたのか。昭和17年(1942)、16歳の著者は滋賀県立八幡商業学校5年生として、ありのままの日常を文章と挿絵で記していた。6月から11月まで約半年間の肉筆日誌を、当時の原稿用紙の罫線や、田河水泡を彷彿とさせる挿絵とともに再現。赤裸々に綴った等身大の記録として平成の世に問う。
電子書籍版も発売中。詳しくは各電子書籍サイト(楽天kobo等)でご覧ください。
今、ここに、十六歳(昭和十七年・旧制中学五年生)の時に記した戦時下の日誌が残されている。 私の学んだ滋賀県立八幡商業学校(明治十九年創立)では、毛筆による日誌を生徒全員に課し、近江商人幹部育成の、精神的支柱の一つとして重視した。私はその中に、いつの頃からか、各ページごとに関連の、挿絵(漫画)を入れるようになっていた。定期的な提出日には、担任の先生から、丁寧な講評と励ましの言葉が返ってきて、ますます乗ってきた。当時としては、校内でも異例の日誌として、職員室で、提出日には、先生方の人だかりができるとの、風評が立って驚いた。学業もさることながら、この日誌習慣が、若き日の個性を磨く場として、大きな役割を果たし、その後の職場活動─老後生活に至るまで、脈々と育ち続けて、ライフワークを豊かにしてくれている。 さて、最近のこと、京都で居酒屋(どん鶴)をやっている、還暦の甥が初めてこの日誌を目にし、異常な関心を示しだした。老朽化(黄変)が進んできた各頁を、せめてもカラーコピーで保存措置をしてくれるという。その間に繰り返し読んだ内容(当時は軍事一色の時代)にまた驚いた。──こんな厳しい時代が、自分達の生まれる前にあったとは、ほとんど知らなかった。ぜひ今の若者達に読ませたい─出版しろ、出版しろと迫ってくる。居酒屋の客にも、関心をもつ人が多いと言う─どうせ一杯気分では……。 しかし、あの時代を知らないとすると、これは困ったことだ。あの戦時下に、国をあげて、みんなが援け合い、必死で頑張った。──その後の血の出るような、再建努力の上に、いまの平和と繁栄がもたらされたことを、古い者も新しい者も、今、もう一度振返りたい。そのよすがとして、赤裸々に綴った、戦時中のありのままの日常を、漫画ともども目を通していただき、当時の資料的な役割が果たせるなら、これに過ぎる喜びはない。

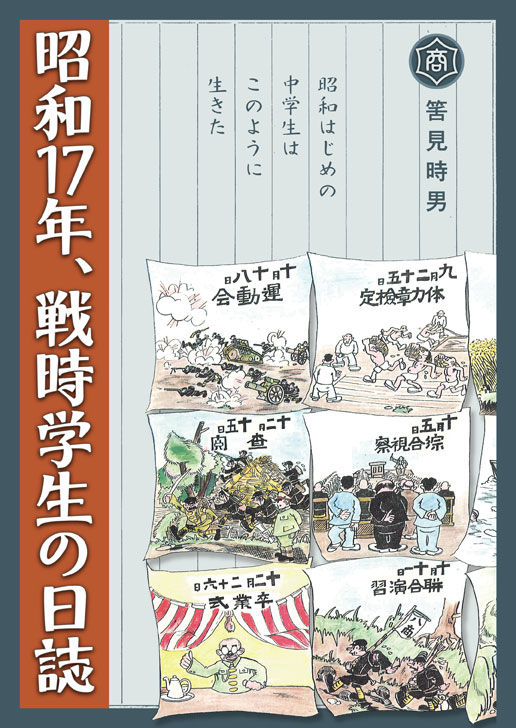
 X
X Facebook
Facebook
 LINE
LINE