
|
山崎 亨さん アジア猛禽類ネットワーク会長、 クマタカ生態研究グループ会長 |

|
寺本憲之さん 日本野蚕学会評議員・ 日本鱗翅学会近畿支部幹事(滋賀県農業技術振興センター) (農学博士) |

|
藤岡康弘さん 滋賀県水産試験場 場長 (農学博士) |

|
高橋春成さん
奈良大学文学部地理学科 教授 |
シリーズの目的
▽「びわ湖の森の生き物」というシリーズが刊行されることになりました。このシリーズ構想の経緯について、“言い出しっぺ”の高橋さんにお話いただけますか。
高橋 一番最初は3〜4年前になるのか、僕らは、機会をつくっては集まり、話し合ってきました。
まず一つ目、一番わかりやすい特徴なのですが、滋賀県は、琵琶湖が中心に語られることが多いのですが、琵琶湖を育む森とそこに棲む生き物については、これまであまり注目されてこなかった。このシリーズでは、そちらに注目してみようということ。
二つ目に、これまでの学会の研究成果を網羅的に紹介したある生き物の概説書といった形ではなく、著者が長年にわたって独自に行ってきた観察記録、調査記録をまとめて一冊にしたいということ。
そして、三つ目にそれらの生き物と人間との関わりを本の中には盛り込みたい。食料としてなど以外に、伝説など民俗学的な話題も含めて歴史・文化的な面も描けないだろうかということ。
▽ご自身は、滋賀県内の里山に出没するイノシシを研究してこられて、文学部の地理研究室に籍を置かれている、生物の研究者としては異色かと思いますが…。
高橋 大学生時代、僕はあんまり勉強もせず、探検部で探検ばっかりしていて。そんな中、卒論で何を研究するかという時に地理の中で生き物を選んだんです。地理の分野でも、人間が住んでいる地域の周りにある自然環境の中には「生物圏」というものがあって、それらとも人間の暮らしは関わるということで、生き物との接点があります。
寺本 今聞くと、最先端の学問のように感じますね。
高橋 まったく逆。近代地理学の創設者の一人とされるドイツのフンボルトなど、昔の学者が確立した非常にオーソドックスな分野です。ヨーロッパ諸国が、アジア・アフリカや新大陸に進出した頃、どこそこの地域にはこういう人間の暮らしがあって、こういう動植物がいるといったことを詳細に記録していった、そういう時代に生まれたものです。
▽なるほど、それぞれの学問分野が専門化する前でもあったということでしょうね。先ほどの三つ目の目的からすると、今回のシリーズは、分かれてしまった諸分野をもう一度統合しようという試みでもあるかと思います。
まだまだ、わからないことだらけ
▽それぞれの原稿を読ませていただいて、まず思ったのは「まだまだ、わからないことだらけなのだ」ということです。素人目で、生物学の分野はDNAの解析が最終局面で、それ以前の段階にあたる生物の生態などはほぼ調べつくされているものと、勝手に思っていました。
ところが、滋賀県という狭い地域、自分の家のすぐそばに棲んでいる生き物のことも「わかっていない」、あるいは「最近になって、著者の皆さんが発見なさったのだ」ということがわかりました。
鳥のイヌワシとクマタカを観察してこられた山崎さんの場合、ちょうど30年前に滋賀県内で初めてイヌワシの繁殖を確認され、その後も仲間の皆さんとともに観察を続けながら次々と謎に包まれていた生態を明らかになさってきた。
山崎 鳥の場合、大学などの研究者を除けば、趣味として野鳥の会などに入って観察しておられる鳥好きも基本的に見て楽しむだけ、写真を撮るだけという方が多いです。けれど、僕らの仲間は社会人になってからも休日を利用して、観察方法や道具なども工夫しながら、イヌワシやクマタカの生態を観察し続けたわけです。
▽山崎さんのグループが鈴鹿山地でイヌワシの繁殖を確認なさった当時、地元の人にイヌワシがいるかどうかを尋ねてみると、「いない」という答えだった。
山崎 それまで図鑑などでも、滋賀県はイヌワシの分布域ではないとしていました。地元の人は飛んでいる鳥は全部区別していたのですが、名前が違っていたのです。本に書きましたが、滋賀県ではイヌワシのことをクマタカ、クマタカのことをハヤブサと呼んでいたんです。イヌワシはさらに区別して、6月ごろに飛び始めた幼鳥を、白い斑紋が翼に3カ所あることから「三ツ星鷹」と呼んでいた。地元の人は夏になると来る渡り鳥だと思っていたことがわかりました。

藤岡 それはサケ・マスの場合もあって、小さい頃はパーマークという小判形の黒い斑点が体の側面にあるんですが、海に下った魚はもう全体が銀白色に変わってパーマークは消えてしまう。だから昔は伊勢湾などでも川で獲れるアマゴと、海で獲れるマスが同じものとは考えられなかったんですね。川から海に下る降海型の種だというのは、明治以降の研究でわかったことで。
寺本 昆虫の場合は、変態によって幼虫と成虫の姿がまったく変わってしまうので、成虫は見つかっていても、幼虫のことはわかっていないような種がたくさんいます。
▽寺本さんが浅井町(現、長浜市)の林で、ブナ科の木(クヌギ、アベマキ、コナラの3種)についたガの幼虫をすべて調べたところ、新種がかなり見つかって…。
寺本 12種類の新種(未記載種)が見つかりました。ガは今、日本で5500種とされているんですけど、まだまだいるんですよ。調査する人がいないだけで、やれば新種はどんどん出てくると思います。
▽寺本さんが入稿されたガの幼虫の写真が面白いんです。本のカラー口絵では、整理してごく一部だけを載せる形になってしまいましたが、近所の林にこんな姿の幼虫がいるというのは知りませんでした。枝や若芽に擬態しているものや、ヒメシャチホコというガの幼虫はアリに擬態していたり…。
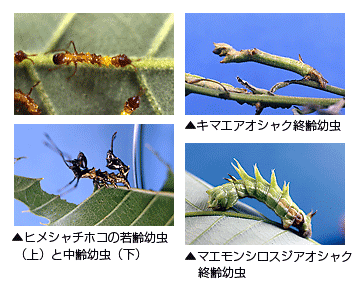
寺本 特に幼虫についてがわかっていない状態です。ガの幼虫は、脱皮するごとに姿がコロコロ変わるものが多いので。
▽まだまだ身近な範囲の生き物もすべては把握できていないんだと思います。このあいだ(9月21日)、NHKで「里山」の番組(『映像詩 里山 森と人 響きあう命』)が放映されましたが、見終わって私はこれから出そうとしてる寺本さんの本の方が「勝った」と思いました(笑)。あの番組の中には一度もガの幼虫も成虫も登場しませんでしたが、寺本さんが調べたところ、クヌギなどにつく昆虫の種数の7割強はガだったわけです。ミツバチやカブトムシなどの甲虫よりもずっと多いガを、あの番組は見すごしている。
寺本 何かことが起こるまで見えていないということは多いんです。例えば、1950年代から化学農薬が多投されるようになって、本来、害虫のそばにいた土着天敵である虫もいっしょに殺してしまっていた。天敵がいなくなったために一層害虫が増えるという現象が、1990年代になってようやくわかり始めた。とにかく多種多様な農薬を多投して目の前の害虫を徹底的に防除する方法から、IPM(総合的害虫管理)と呼ばれる、適期に適種の周辺環境に影響が少ない化学農薬を用いる方法に変わりつつあります。つまり、省農薬は消費者のためではなく、生産者が将来的に防除しやすくするためのものということです。滋賀県で推進している環境こだわり農業は、一般的に消費者の食の安全・安心ためのイメージが強いのですが、実は、生産者のためのものでもあると言えるのです。
▽続いて、藤岡さんの場合は、ビワマスで雄にだけ現れる河川型を発見なさった。
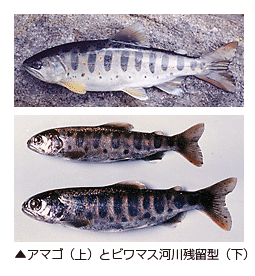
藤岡 河川型、あるいは河川残留型とも呼んでいます。
▽琵琶湖に戻らずに、川に棲みつづける。アユの場合は…。
藤岡 琵琶湖のアユの場合の特殊性は、全部が川に上るんじゃなくて、かなりの割合で湖に残ったままになる、河川残留ではなくて湖残留になることです。雄雌に関係なく。ビワマスの場合は、秋の産卵期に生まれて、4〜5月、場合によっては7月ぐらいまで川で育って、一部の雄を残してすべて琵琶湖へ下ってしまう。
▽面白かったのは、最初「いるだろう」と仮説を立てられたのですね。
藤岡 そうです。
▽それまで、誰も気づかなかったというのも不思議なんですが。
藤岡 アマゴとビワマスは形がほとんど同じなので、川に残っているのはすべてアマゴ、琵琶湖へ下るのはすべてビワマスと思われていたわけです。それは仕方がないと思います。
ところが、池でビワマスを飼ってみると、生まれた翌年に成熟してくる雄が出てきたんです(大多数は成熟するまでに3〜4年かかる)。1年で成熟してしまう雄を「早熟雄」と呼んでいます。同じような雄は、サクラマスなどにも現れるので、ビワマスの早熟雄は「琵琶湖へは下らないだろう」と予想できたのです。その後で、河川で調べてみると、実際に残留型の雄がいました。
食べ物と進化の関係
藤岡 サケ・マス類は、最初から海水に下れる能力があるわけではなくて、直前に甲状腺ホルモンや成長ホルモンが出ることでその能力がつくとされています。成長ホルモンの作用で、海水に下ると同時に急激に大きくなります。ところが、ビワマスの場合は、下る琵琶湖も淡水ですからそれを気にする必要はないかわり、成長がとてもゆっくりだという特徴があります。
▽琵琶湖でのエサは何でしたか。
藤岡 琵琶湖にしかいないアナンデールヨコエビという生き物です。これが1年しか生きない種で、8〜9月に世代交代が行われて、大きな親の世代がいない期間が生じます。それもなかなか大きくならない要因でしょう。なら、他のスジエビなどをエサにしたらよさそうなものなのに、食べない。なぜ他のエサを食べないのかわからないんですが、胃の中からはアナンデールヨコエビ以外は出てこないんです。偏食というか、固有種にはありがちなんですが。
寺本 昆虫でもそういう例がよくあります。有利性から考えたら、どんな植物でも食べた方がよさそうなのに。
藤岡 そうですよね。気候変動があった場合のためにも。
寺本 ガの場合、一生が短くて年に何回も産卵が行われる種もいるので、種分化のペースも速いんです。僕の本では、その辺について考えていて、種分化のあり方というのは、大陸移動などによって生じた「異所性種分化」とは別に、食べ物が違うことによって起こる種分化もあるんじゃないかという提案をしたんです。突然変異で1匹が今までとは違う植物を食べることができるようになると、同じ地域にいても隔離が行われる。それが何世代も続くと、外観も異なる別の種が生じるということになるのではないか。「異食性種分化」という呼び方をしたんですが。
▽また、NHKの番組ですが、先日(10月3日)、クロスズメバチの巣を襲う猛禽類のハチクマの生態を紹介してましたね(『ダーウィンが来た! 生きもの新伝説』第118回「目撃!タカ対スズメバチ」)。
藤岡 あれは、びっくりしました。
▽山崎さんの本の中では、ハチクマは主に渡りをするという生態が紹介されているのですが。いろいろ食べ物がある中で、なぜあんな危険なものを食べるように進化するのでしょう。
山崎 何か資源があればそれも利用しようとする種が現れるのは当たり前で、ハチの子なんてのは非常に栄養価が高いし、一時的に数が増えるから、繁殖期の栄養源としてとても使いやすいわけです。だから、ハチを食べるタカというのは世界中にいます。
一同 そうなんですか!?
山崎 ヨーロッパにはヨーロッパハチクマ、中南米にはアカノドカラカラというハチを食べる種がいて。例えば、変わった生物を食べる猛禽としては、中南米にタニシやカタツムリを食べるトビがいます(笑)。カタツムリを貝から引っ張り出しやすいように、くちばしが鉤状に長くなっていて、タニシトビといいます。だから、鳥の研究者としては、ハチクマの食べ物は何も不思議ではなくて、それよりは渡りの生態の方が「すごいな、謎やな」と思う。
ビワマスの例にも似ていますが、東南アジアには留鳥、一年中そこにいるハチクマがいます。ところが、わざわざジャワ島から日本まで渡りをするハチクマもいる。
▽その番組は長野県での調査でしたが、ハチクマは滋賀県にも来てるんでしたね。
山崎 広く青森の方まで渡ってきます。冬の間は、留鳥と渡りをするハチクマがいっしょにジャワ島にいる。なぜか?
藤岡 向こう(ジャワ島)でも、食べ物はハチなんですか?
山崎 そう。ジャワ島は熱帯なので、乾期と雨期が徐々に島の中を移動していく。雨期で花が咲いてると、ハチなどの昆虫がたくさん発生する地域が島の中で移動していくので、ハチクマもそれに合わせて移動していきます。
僕の予想としては、渡りをするハチクマは、これはこれで別の種になっていく可能性もあるのではないかと思います。別の猛禽類でサシバという鳥がいて、夏に日本に渡って来ると水田の昆虫やヘビ、カエルなどを食べる「里山のタカ」として有名なんですが、留鳥のサシバはいません。
▽それは、渡りをするタイプが種として確立されたわけですね。
山崎 その可能性はあると思います。この種は留鳥なので、すでに種分化が終了した状態であるのかも知れません。
藤岡 サケ・マス類でも、この辺にはいませんが、北海道の阿寒湖に棲むヒメマスの降海型にあたるベニザケという種がカナダなどにいます。昔、リッカーという研究者が、ベニザケはいったん湖に入って、海に下るタイプとそのまま湖に棲みつづけるタイプとが生まれて、その区別が種が分化するきっかけだったのではないかという説を言っています。鳥類でもまったくいっしょだなと、今思いました。
寺本 昆虫のある研究者は、「種」というものはないんだということを言ってます。どの種もガチガチに定義してしまうと説明のつかないものが出てくる。ちょっと食べ物が違うとか、習性が違うとか、段階的に亜種とかの区分も行っていますが、かなり曖昧なものも多い。分類は意味がないということではなくて、もちろん害虫対策でもこの虫として特定する必要はあるんですが。
▽明暗や色調が徐々に変わっていくことをグラデーションといいますが、そんなふうに連続性があるということでしょうか。
藤岡 それは僕もそうだと思いますが、やはり種というものを決めておかないと、研究対象がなんだということになってしまいますよね(笑)。
それで思い出しましたが、我々研究者の間で問題になっているのは、「本当に滋賀県にはアマゴがいたのか?」ということです。見た目では、アマゴとビワマスは区別がつきにくいですから、昔からアマゴと思われていたものは、ビワマスの河川残留型かもしれないわけです。
▽それは大問題じゃないんですか(笑)。
藤岡 実際、これまでアマゴと認識されてきたものは、大多数がビワマスの河川残留型だったのだろうと思います。まったく滋賀県の川にアマゴはいなかったというわけではなく、少数ながらいたと私は思っていますが。
「びわ湖の森」は自然ではない
▽それぞれの原稿自体は、あまり他の執筆者の内容を意識せずにお書きになったと思うのですが、読ませていただいて、人間がつくってきた二次林、最近では「里山」と呼ばれるものの主体だったドングリの木、ブナ科コナラ属の落葉樹が共通したキーワードになるのではないかと思いました。ドングリの実や葉を食べる、あるいは葉が落ちることによって猛禽類の狩り場ができるといったことでさまざまな生き物と関わりがあります。
高橋さんの調査によると、イノシシは春先から稲の収穫期ごろまでは集落と農耕地周辺にいて、その後の木の実のシーズンには山側に移動するというように、行動範囲が明確に変わっているそうです。また、ニホンカモシカ関係の本をみていたら、伐採された直後の広葉樹林で若芽を食べるという調査結果が載っていました。ニホンカモシカは人間とあんまり関わりがないようですが、人間の活動に適応するような形で生活しているらしい。
山崎 当たり前ですが、人間はものすごい長い期間、山の木々を利用してきたわけです。戦後の大規模な開発手法ではなく、持続的に利用するようなやり方で数百年、数千年やってきてる。その中でうまく適応して生き残ってきた種が、今、日本の「野生動物」といわれているものなわけです。
つまり、逆に人間の影響がまったくなかった状態が続いていたら、日本の生物種はまったく違ったものになっていただろうともいえます。特にイヌワシなどは、まったくの自然状態では日本に棲息するのは困難だっただろうと思います。だから、「まったく手をつけない自然が最高だ」と多くの人が考えてしまうと問題があるのです。
▽「自然」という言葉を安易に使わない方がよいということですね。「びわ湖の森」も自然ではなく、人の手が加わったものである。木々に包まれた山も、昔の人の感覚でいえば、食料・燃料・建築材がある、金になる場所として、田んぼや畑と地続きだったわけですから。そういう目で眺めてみる必要があると。
滋賀県の場合でいえば、琵琶湖岸のヨシ原は、刈り取りなど人間の手を加えなければ維持できない場所として徐々に認識されるようになってきていると思うのですが。
山崎 イヌワシやクマタカの保護を話すとき、イヌワシ・クマタカを手つかずの原生林のシンボルのようにとらえて、手を触れてはいけないみたいな意見にはどうしても同意できないんです。現在のスギ・ヒノキの植林が50%を超えてしまっている状態がまずいのはもちろんですが、それ以前の数百年、数千年、維持されてきた環境の歴史を知ったうえで考えるべきです。
種の多様性という点からも、滋賀県のような多種類の広葉樹が育つ地域は、非常に重要だし。特に食物連鎖の頂点に立つ猛禽類は、その下位の多様性が失われると変動をもろに受けてしまう。
寺本 僕の本でも最後の方でふれていますが、人の活動によって種の多様性が生まれた、維持されたという面が確実にあるわけで、その生まれた多様性による恩恵も被ってきたのだから、もう必要ないといって放り出すのはまずい。もっと大きな話にすると、種の存続、種の延命にもつながるものだからだろうということですね。
僕は勤務先で、高橋さんと獣害対策の仕事をしてきましたが、県内の森に入った時も、林の中の下草というとシダ植物ぐらいしかなかったり、単一なスギの木しか生えていなかったり。やはり、人が管理して初めて森林の生き物の多様性も維持できるんだという部分を広く知ってもらう必要があると思います。
高橋 ただ、昔の話をするとね。いわゆる里山も、僕らが初めて入った昭和40年代後半から50年代の方がむしろ荒廃していた印象がある。だから、今は里山が理想化されすぎてるようにも思う。それはもちろん理想的な状態を維持してきた地域もあるかもしれないですが、僕が見てきたのは、過度に木でも何でも取りすぎて、土壌浸食したといった地域が多かった。
▽それは、滋賀県内ですか。
高橋 いいえ、広島大学だったので中国地方の山間部を調査しました。
▽中国地方の、特に山陽側だったからというのはあるかもしれません。瀬戸内海沿岸で古代から行われた製塩のために燃料にする広葉樹の伐採が進んで、二次林がアカマツばかりになっていった地域ですよね。
高橋 そこまで荒廃すると、イノシシも何も寄りつかないので被害もないわけですが。バランスのとれた場所というイメージがあるけど、現実はもっと荒れ果てた場所だったと、僕の記憶にはあります。
でね、僕が取り組んできたのは獣害対策だけど、それだけでは集落全体を巻き込んだ活動は難しいと思う。実際にはそんな所はそうそうなかったのかもしれないけど、生態系のバランスのとれた場所としての里山のことを広く知ってもらう必要はあるでしょう。
それから里山に対して、山崎さんの扱った「奥山」でも適度な攪乱、適度な資源利用が行われることで、そこの生き物たちの生活が保たれていたわけでしょう。
▽山崎さんの本によれば、イヌワシがなぜ日本に棲みつづけているかというと、一言でいえば伐採地があったからということですね。
山崎 それも大きな要因のひとつです。ここで強調しておきたいのは、「里山と奥山の違いはあまりない」ということ。日本の場合は、奥山にもある程度は人の手が必ず入っていたんです。これは高度経済成長期以降といった最近の話ではなくて、江戸時代、その前の中世の時代から、里山は里山の使い方、奥山は奥山の使い方というものが確立されていて、それがなかったら、たぶんイヌワシは日本に広く分布し、多くの地域個体群を維持することはできなかっただろうと思います。それが戦後の植林政策で一気に伐採して、一気に広範囲にスギ・ヒノキを植林するというふうになった、この50年の変化がイヌワシに打撃を与えたということです。
最近は確かに、里山については人の手が入る必要があるという考えを持っている人が増えてきたと思います。問題は、それを知った人は逆に「奥山」に対しては、人の手をいっさい入れてはいけないと思う場合が多いということ。
イヌワシの調査で鈴鹿山脈の奥の方に暮らしている人たちと話して、だんだんわかってきたのですが、もちろん里山に比べると奥山を神聖視するという感覚はある。けれど、それは神様がどうこうというのではなく、山崩れなどの災害に対する恐れ、乱伐が過ぎると、下手にやると恐いぞという災害や資源の枯渇から生活を守るための知恵であると思います。
▽江戸時代には、轆轤(ろくろ)で木を削って椀などの器の木地をつくることを生業とする木地屋と呼ばれる人々がいました。愛知(えち)川上流の小椋谷(おぐらだに)が根元地とされ、滋賀県と非常に関わりが深い人々ですが、彼らは山の8合目より上の木なら自由に使ってよいとされ、切ってなくなったら他へという移住をくり返していた。逆にいうと、8合目というかなりの奥山までは麓の村々の森として利用され、勝手に入って炭を焼いたといった理由で村どうしの訴訟がよくあったようです。
その木地屋が使った木の中でも多かったのが、高地に生えるブナやトチなんだそうです。ブナは木偏に無と書くとおり、役立たずの木とされていたんですが、柔らかいので轆轤細工には向いていた。
山崎 僕はイヌワシやクマタカの調査で、木地師の発祥地である蛭谷(ひるだに)・君ヶ畑(きみがはた)に昔から通っています。木地屋さんが使用したのは、ブナだけでなく、トチ、サクラ、ケヤキなどさまざまな種類の樹木です。それほど多種類の樹木があったということですね。ところが、明治以降、木地屋制度がなくなっていったのは、戸籍制度の改革や国有林ができたためではないかといわれています。
▽そう。江戸時代に無所有だった一帯が国有林となって残ってしまった。原生林として残っているのもそのためです。ですから、ブナ=自然というイメージが一般に強いと思いますが、ブナ以外のブナ科植物に注目してほしいなと思うようになったんですが。そちらの二次林が一番、人間との結びつきもあったわけですから。
藤岡 木地屋は、魚との関係も深いんですよ。彼らは山から山へ移り歩いて当然魚も食料にしていた。そのために、自分たちで魚を別の谷へ移したこともあったようです。分布域を広げる役割を彼らが担っていたということはあったでしょう。
山崎 それは充分考えられる。
藤岡 もちろん伝承としてしか残っていませんが、それを拾い集めて本にまとめている人もいるぐらいで。だから、琵琶湖の上流の川のいくつかには本当に上流のところまでアマゴがいるんですが、それは本来の自然分布でそこにいるのか、人によって移植されたものなのかというのはわからないんですよ。
▽本当に人間の手というのはすみずみまで入ってますよね。
山崎 日本の場合、手の入っていない所を探そうたって無理。特に滋賀県みたいな便利な場所は、周りの山々の至る所に隣の国とつながっていた峠があって、交易の場として行き来が絶えずあったわけでしょう。
藤岡 谷筋には川が流れているし、こっちから何か桶にでも入れてあっちの谷にというのは簡単だったはずで(笑)。そんなふうに魚の分布にも影響を与えてますね。
寺本 最近、ギフチョウやオオムラサキが少なくなって、アマチュアの愛好家がギフチョウを自分で飼育して、もともとギフチョウがいたとされる所に放蝶している例があるんです。いったん死滅してしまった地域に他から導入することに対してはどう考えるか、学会では注意をうながしています。
絶滅までいかない状態で、里山の雑木林が手入れされなくなったために減少していたゼフィルス(翅の光沢が美しいシジミチョウ類)を、私たち日本鱗翅学会近畿支部も関わり、木々の伐採や下草刈りによって復活させた三草(みくさ)山(大阪府と兵庫県境)トラスト活動などは意味ある里山保全活動と考えますが、単にその地域の個体数が減少したから、他地域からその昆虫を採集して導入したりそれを増殖してそこへ放すことは、やってはならないことで、これは本当の環境保全活動ではありません。残念ながらこのように勘違いしておられる自然愛好家が少なくありません。その地域の土着種と、さらにそれらと関与するエサとなる食樹や食草などの周辺環境も総合的に人によって再生してやることが重要です。
▽昔の人間の行為によってかなり攪乱されているが、では現在の行為に対してはどこを基準にすればよいのか。その点は、研究者や保護活動を行っている人の間でも意見の相違があるでしょうね。
森林は資源だと考える
▽ところで、森の木々はビワマスにも何か関係しますか?
藤岡 原稿ではあまり書けていないんですが、川で育つ期間に、川の水面に落ちてくる昆虫を食べますから、「河畔林」と呼ばれる、川の畔に生えている林の役割、それがいかに維持されているかは重要です。葉が落ちればそれを食べる水生昆虫が育って、ビワマスがそれをエサにします。エサの供給だけではなく、葉が茂ることで太陽光をさえぎって水温をあまり上昇させない働きもあるので、特に広葉樹の役割はビワマスにとっても大切だと思います。実際、研究としては難しくてあまり行われてきませんでしたが、最近は少しあるようです。
▽琵琶湖南端から出土した縄文時代の粟津(あわづ)湖底遺跡では、一番多い哺乳類の骨というとイノシシで、木の実としてドングリの実の殻も貝塚のように堆積しています。遺跡から出土する魚類の骨としては、フナなどのコイ類は多いようなんですが、調査報告書をみてもビワマスというのは出てきません。これが不思議だったんですが?
藤岡 おそらく、あまり出ていないと思います。サケ・マス類は頭部も含めて骨のほとんどが軟骨なんですよ。だから、土中ですぐ溶けてしまって残りにくい。コイ科魚類は硬骨、石灰化した硬い骨だから残る。ですから、想像になってしまうんですが、縄文時代の琵琶湖周辺でもビワマスはよい食料になっていたでしょう。
▽最後に個人的なことを言うと、私は湖北の郡部に住んでいるので、7月頃は平地でも山でも緑が濃すぎて車で走りながら周りを見ると「恐い」です。7月末に大字総出の川掃除があって、まだ護岸がコンクリートにもなってないので、土手に生えた竹藪がどんどん繁って川面を覆うのを毎年切るんです。今年は役場から竹を粉砕する機械、シュレッダーみたいなのを借りてきて…。
寺本 チッパーという機械ですね。
▽それを使ったんですが、雨降りの日だったからビショビショの竹を入れたのが悪かったのか、壊れちゃって(笑)。
寺本 リースでも高いですよ。あれ(笑)。
▽だから、自然の管理はものすごく大変、ほっておくとどんどん押し寄せてくるイメージがあります。
寺本 竹林も、もとはそれを利用するために集落で植えたものですよね。
▽そう。昔の農具とか竹製が多いですし。家の壁にも使ったり。江戸時代であれば、竹林も年貢の対象だったぐらいで、有用で価値があったんですよ。
寺本 スギやヒノキの人工林でもそうです。使うために植えたのに、時代が変わって売れなくなったから管理しないということになってしまった。
山崎 やっぱり、人がそれを利用して循環するようなシステムになってないと続かない。今の感覚とは逆に、国土の60%以上が森林なら、それだけすごい資源があるんだという考え方にならないと。資源として活用できたから山地に千数百年にわたって人が暮らしてこられたのだし。その資源を使うシステムをもういっぺん考え直してこそ、野生動物も棲みつづけることができるんだと思います。
▽話が大きくなると結論がすぐには出ないでしょうが、とりあえず、このシリーズでは身近な生き物たちの知られざる生態を紹介していけたらと思いますので、執筆者の皆さん、それから読者の皆さんよろしくお願いいたします。
(2008年7月28日と10月9日の2回にわたる座談会を編集のうえ掲載。)
|
正直に申し上げると、私は生物一般について無知である。今回の座談会は知ったかぶりをしながら切り抜け、原稿にするさい司会役である自分の発言にかなり加筆して5割増し賢くしてある。ボイスレコーダーの録音データを聞きながら、ずれた応答をしている箇所に赤面し、掲載した中には出てこないが、ボセンカイキという言葉が頭の中で漢字に変換できなかったのを思い出した(母川回帰)。そんな私でも理解できる生き物の生態についてのシリーズになるので、ぜひ手にとっていただきたい。 |


 サンライズ出版
サンライズ出版